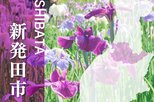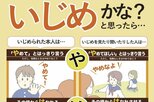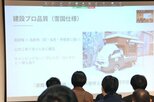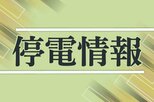新潟県の推計人口が戦後初めて210万人を割った。人口減少のペースは年々速まっており、約4年間で10万人減少した。日本の総人口が減り続ける中、新潟県の人口を増加に転換することは容易ではないが、減少幅を緩やかに抑えることはできるかもしれない。人口問題に詳しい日本総研上席主任研究員の藤波匠氏(59)に聞いた。(報道部・桑原健太郎)
- ついに…新潟県推計人口、戦後初210万人下回る 人口減少ペース加速
- ピークの1997年から、聖籠町を除き減少…新潟市「ダム」の役割果たせず
- 減少率最大の阿賀町はピークの半分、子ども激減 充実した子育て環境、成果まだ
-2008年に240万人を割り込んで以降、10万人減るペースが7年、5年、4年と加速しています。
「10万人減っていくペースは当面、上がりこそすれ下がることはないだろう。新潟県の年間死亡数は約3万3千人で出生数は約1万1千人、自然増減数はマイナス約2万2千人になる。戦後すぐに生まれた団塊世代が80歳近いので、亡くなる人は今後さらに増えていく。毎年2万〜3万人は確実に減っていく。そこに数千人規模の人口流出が加わることになる」
「自然減が多いので人口減少のペースが速いのはやむを得ない面がある。そこばかり気にしてしまうと、人口減少や少子化対策の方向性を見誤ってしまう可能性がある」
-県内でみると阿賀町や関川村、佐渡市といったもともと人口が少なく、県境にある市町村などで人口減少が際立っています。
「いわゆる過疎地域ほど人口減少が顕著になるというのは全国的な傾向だ。高齢者が多く、産業がなく、交通の便が悪い。結果として若い人が出て行ってしまう。新潟県のように中山間地域を多く抱える自治体は、人口流出の傾向が強く出てしまう」
-対策はありますか。中山間地域は国土保全の視点からも重要とされます。
「とにかく産業を生み出し、雇用をつくることだ。高齢者ばかりでは、手を尽くしても消滅する地域は出てきてしまうだろう。それは致し方ない。人が住み続けるには富を生み出していくことだ」
「今、山の価値が見直されている。和歌山県に『木を切らない林業』を売りにする株式会社中川というベンチャー企業がある。植林や育林、子どもへの教育事業などを手がけており、注目されている。二酸化炭素を吸収する森を育て、(温室効果ガスの排出削減量を売買する)クレジット取引で収益を上げる仕組みだ。脱炭素や持続可能な開発目標(SDGs)に力を入れる大手企業が次々とクレジットを求めているという」
「30人を超える雇用があり、...