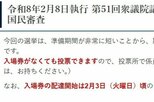政府は29日、首相官邸で原子力関係閣僚会議を開き、原発立地地域の避難道路整備など公共事業を財政支援する「原発立地地域の振興に関する特別措置法」(特措法)の対象範囲を拡大することを正式に決めた。東京電力柏崎刈羽原発柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は主に関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に、6号機は2025年に全ての審査に「合格」した。7号機は2024年6月に技術的には再稼働できる状況が整った。再稼働東京電力福島第1原発事故を受け、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。の地元同意新規制基準に合格した原発の再稼働は、政府の判断だけでなく、電力会社との間に事故時の通報義務や施設変更の事前了解などを定めた安全協定を結ぶ立地自治体の同意を得ることが事実上の条件となっている。「同意」の意志を表明できる自治体は、原発が所在する道県と市町村に限るのが通例につなげたい考えで、石破茂首相は「再稼働への理解が進むよう全力で対応を進めてほしい」と関係閣僚に指示した。
東電に対する地元の根強い不信感を払拭するため、官房副長官をトップに省庁横断の「監視強化チーム」を設置し、柏崎刈羽原発の運営をチェックすることも決めた。
閣僚会議には東電の小早川智明社長も出席。地元理解を得るため、地域経済の活性化に向けた資金的な貢献や、脱炭素、デジタル化に関わるGX・DXへの事業投資に努める方針を明らかにした。
特措法の対象地域については、現在の原発から半径10キロ圏内を半径30キロ圏内に拡大する。本県では、東京電力柏崎刈羽原発から半径5〜30キロ圏(UPZ原発などで事故が発生した場合に防護措置を行う区域の一つ。原発からおおむね5~30キロ圏は緊急防護措置を準備する区域=Urgent Protective action planning Zone=とされる。放射性物質が放出される前に屋内退避を始め、線量が一定程度まで高くなったら避難などをする区域。5キロ圏はPAZ=予防的防護措置を準備する区域=という。柏崎刈羽原発の場合、柏崎市の一部(即時避難区域を除く全ての地区)、長岡市の大半、小千谷市の全域、十日町市の一部、見附市の全域、燕市の一部、上越市の一部、出雲崎町の全域が当たる。)内の小千谷、十日町、見附、燕の4市が新たに対象となる見込み。これまでは柏崎、刈羽、長岡、上越、出雲崎の5市町村だった。国は今後、地元の意向を踏まえ、対象地域を決める。
対象地域になると道路や教育施設などのインフラ整備にかかる国の補助率が最大55%にかさ上げされるなどして、地方負担は最小で13・5%に軽減される。県内への2023年度の国からの補助額は6億3千万円だった。
避難道の整備を巡っては、柏崎刈羽原発から6方向に延びる幹線道路を国が全額負担することになっている。特措法の対象地域では、幹線道路に接続する支線道路の整備で地元の負担軽減になると期待される。

東電福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。後、避難計画原発事故時に住民らが避難する場所や経路、移動手段を盛り込んで自治体が策定し、政府の原子力防災会議が了承する。東京電力福島第1原発事故後、策定が義務付けられる範囲は原発の半径10キロ圏から30キロ圏へと拡大された。事故時に5キロ圏の住民は30キロ圏外に避難し、5〜30キロ圏は屋内退避を基本とし放射線量が高くなった場合は避難する。の策定義務が原発から30キロ圏内の自治体に拡大され、防災対策の充実が求められるようになった。一方で特措法の対象地域は見直されず、花角英世知事は5月に対象拡大を要望。6月には全国の原発立地地域の知事らと、石破首相に直接要請した。
花角知事は29日、報道陣の取材に「国が前面に立って地元の理解を進めていくと言ってきた中で、取り組みを進めてもらった。県民の安心感につながるかどうかを確認していきたい」と述べた。
再稼動実現の掛け声に終わらぬか、注視を
29日の原子力関係閣僚会議で決まった原発の理解促進策は、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を後押しする政府の強い姿勢を印象付けた。財政、防災、経済効果など、県内の自治体などからあった要請への「回答」をそろえたかのような内容で、裏を返せば、再稼働への地元同意を迫る圧力にも映る。

会議では、全国でも要望が強かった原発から半径30キロ圏への財政支援の拡大を決めた。一方で、その他の項目は、ほぼ柏崎刈羽原発に特化した内容だった。
地元で不信感が根強い東電の原発運営に対する監視強化をうたったほか、閣僚会議に東電の小早川智明社長を同席させ、地元経済対策も打ち出させた。
原発政策で国が前面に立つよう求める声に応えたと捉えることもできる。だが、原発事故時の避難対策の改善では、かねて地元から挙がっている大雪など複合災害時の懸念を解消するまでの具体策は見えない。柏崎刈羽原発の運営を監視する組織も、関係省庁の幹部をそろえたものの、どのような役割を担うのか不明点が多く、効果は未知数だ。
今回打ち出された一つ一つの対策は具体化や実効性を伴わなければ、政府が再稼働を実現させるための掛け声に終わりかねない。住民の安全確保や懸念解消に資するのか注視が必要だ。
理解得るため…地元に資金提供 中越沖地震では30億円
東京電力の小早川智明社長は29日、首相官邸で開かれた原子力関係閣僚会議に出席し、柏崎刈羽原発再稼働への理解を得るため、地元への資金援助を行うと表明した。...