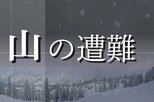JR只見線(新潟県魚沼市-福島県会津若松市)は、2011年の豪雨災害で不通となった福島県側の一部区間の復旧を終え、10月1日に全線が再開通した。只見線の復活は、経営の厳しい赤字ローカル線の「奇跡」と言われる一方、存続に向けた取り組みはこれからが正念場となる。新潟県唯一の沿線自治体である魚沼市で、11年ぶりの開通を待ちわびる市民の思いと利活用に向けた課題を探る。(3回連載の1回目)
「全線再開通」「小出-大白川開通80周年」「只見線に手を振ろう」-。思いを込めた三つののぼり旗が、魚沼市内にある八つの駅にたなびく。
厳しい暑さが続いた7月末、魚沼市の沿線住民でつくる「だんだんど〜も只見線沿線元気会議」の会長、横山正樹さん(71)は只見線の各駅を回り、汗をぬぐいながら旗を並べた。「再開通が決まって、今はほっとした気持ち。皆さんの願いがやっとかなう」と笑みを見せた。
2011年7月の豪雨災害で福島側の一部が寸断された只見線。元気会議はその直前の3月に、ふるさとの鉄道を応援する団体として発足した。
14年から会長を務める横山さんは、再開通にかける福島側の熱意を目の当たりにしてきた。JR東日本が当初主張したバス転換案から、自治体が維持費用を負担する方式での復活が決まり、「只見線を軸にした取り組みに覚悟を持ったことがJRを動かした」と感じる。
その福島の思いも原動力に、元気会議は再開通を見据えた活動を展開してきた。県魚沼地域振興局と魚沼市の支援を得ながら、只見線の歴史や魚沼の魅力を発信するパンフレットを作成。只見線を使った紅葉ツアーを企画した。市民に関心を持ってもらおうとシンポジウムや沿線の植栽、福島との住民交流も手がけた。
「これまでは基盤づくりだった」と横山さん。再開通後は、只見線を利用した交流人口の増加で地域を元気づけてほしいといい、「自分も会津の宝を探しに行きたい。みんなが只見線で小さな旅をしてもらえたら」と期待をかける。
■ ■
半世紀前の1971年8月に実現した只見線の全線開通は、沿線住民の悲願だった。豪雪地にとって地方と東京を結ぶ足であり、観光面も期待された。
「だんだん出来上がっていくのがうれしくて、只見線の発展に夢を持っていた」。約60年前、中学生だった魚沼市の佐藤道博さん(73)は、最後の未開通区間だった大白川-只見間の工事現場に足しげく通い、カメラに収めた。
佐藤さんは就職後も通勤に利用し、休日は会津側に乗って出かけるなど、誰よりも乗り支えてきた。全線開通から51周年となった今年の8月29日は、仲間とともに乗車してささやかに節目を祝った。
「朝一の列車で会津川口ぐらいまで行くと、ちょうど良い旅になるんだ」と心待ちにする一方、乗客が減りゆく様を見続けただけに、不安も募る。「再開通で人が増えるのはいっときかもしれない」
■ ■
再開通を機に、新たな交流を育もうという動きも芽生えている。市内有志らのグループ「つながる135・2」は、福島県柳津町にゆかりのあるピアニストとともに、10月29日に魚沼市でコンサートを企画。その後は柳津町などでも開く予定にしている。
代表の諸橋雅枝さん(55)は「赤字路線なので正直、つながらないと思っていた。でも、福島県の人たちが話し合って復旧が決まり、地域に愛される大事な存在だったと分かった」と振り返る。
沿線各地の特色をイメージした缶バッジも販売し、復活ムードを盛り上げている。「再開通をきっかけに只見線の応援を続けて、人と人、地域と地域のつながりを大切にしたい。人口が減る地方で、それが新たなエネルギーになれば」と思い描いた。
◆只見線とは?豪雨被害の状況は?
小出(魚沼市)と会津若松(福島県)を結ぶ只見線は135・2キロ、36の駅がある。新潟県側は1942年11月1日に小出-大白川間が開通した。福島県側は63年までに会津若松-只見間がつながった。71年8月29日に只見-大白川間が開通して全通。
2011年7月の新潟・福島豪雨で会津川口-只見間の3カ所の橋梁が流失し、27・6キロが不通となった。同区間はバスによる代行輸送を実施した。
復旧に向けては、福島県と同県内の市町村が復旧費約90億円のうち3分の2を負担。さらに不通区間の鉄道設備を保有し、年間3億円の維持費も担う「上下分離方式」の採用に踏み切った。

新潟・福島豪雨から約1年後の只見線第5只見川橋梁=2012年7月、福島県金山町