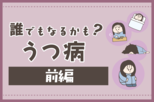都内で開催中の「第38回東京国際映画祭」で30日、91本目の最新作『TOKYOタクシー』(11月21日公開)を控える山田洋次監督と、歌舞伎役者の生きざまを描いた大ヒット作『国宝』(公開中)の李相日監督による対談イベントが行われた。
【写真】豪華だ⋯真剣な顔つきでトークする山田洋次監督&李相日監督
山田監督は自身の新作よりも『国宝』への関心が高かったようで、司会者が話題を切り替えようとすると「話を(『国宝』に)戻していいですか」と切り出す一幕も。俳優の演出から構成設計、編集術、“古典芸能と映画”の親和性、日本映画の海外展開まで、縦横無尽に語り合った。
李監督は、興行収入160億円を突破し歴代記録に迫る『国宝』について「記録というものはいつか必ず更新される。その時代ごとに観客が求める作品が記録をつくっていく。何が要因だったのかを振り返るのは、もう少し後になると思います」と冷静にコメント。
一方の山田監督は『国宝』の構成力を絶賛。「二人の男の物語を軸にしながら、女性の三角関係を置かず、“芸”や“血筋”という不条理を中心に据えている。難しいテーマをきちんと表現していて驚いた」と語った。
これに対し李監督は「その発想は原作者・吉田修一さんの力が大きい」と応じた上で、「二人の存在によって“芸”と“血筋”という対立軸が生まれた。嫉妬や競争を超えて芸に身を捧げる二人の間に絆が生まれる――その美しさを描きたかった」と明かした。
山田監督はまた、女形を演じた吉沢亮と横浜流星についても「すばらしかった」と称賛。李監督も「稽古開始から撮影まで約1年半。すり足から始め、撮影中も稽古を続けた。互いに高め合った時間が、物語の関係性にも現れた」と俳優陣の努力を称えた。
さらに話題は、『国宝』で人間国宝の女形・万菊を演じた田中泯へ。山田監督の『たそがれ清兵衛』(2002年)への出演以降、俳優としても活躍の場を広げた田中について、山田監督は次のように語った。
「顔がいい、声がいい、体が動く――そこに賭けたんです。でも下手くそでどうしようもなかった(笑)。それkら20年たっても同じ芝居をしている(笑)。でも、それが彼の値打ち。そこにいるだけでいいと思わせる存在なんです。それを20年もやっていると、“笠智衆”のようになってくる」と山田監督は笑う。「笠さんは若いころから本当に真面目で、一人で黙々と稽古をする人だったけれど、全然上達しなかった(笑)。それでも小津安二郎監督は、そうした笠さんをとても評価していた。もう、いるだけでいいというかね。そこにいるだけで成立してしまう。芝居よりも“存在そのもの”が価値なんです。田中さんも、いままさにそういう俳優になりつつあると感じます」と話した。
一方、『TOKYOタクシー』には木村拓哉が出演。フランス映画『パリタクシー』(監督:クリスチャン・カリオン)を日本を舞台にリメイクした作品で、冒頭では原作にはない朝食の場面が登場する。「前の年に木村さんはパリの一流シェフを演じていたから、『僕の組では納豆か』って感じだったけど、本人は真剣に納豆をかき混ぜていましたね(笑)」と山田監督。
李監督が「『武士の一分』(2006年、監督:山田洋次)のときと比べて、木村さんに変化を感じましたか」と尋ねると、山田監督は「むしろ同じように真面目だと感じました」と即答。「彼は“きちんとやらなきゃいけない。それが自分だ”と考えているんじゃないかな。出番が終わっても最後までセットに残り、出番がなくても最初から現場に来る。そういう生き方を自分の中で決めているんでしょうね。なかなか、ああいう男はいません」と、感心したように語った。
また、『国宝』が「第98回米アカデミー賞」国際長編映画賞の日本代表に選ばれたことに関連し、山田監督は日本映画界の課題にも言及した。「日本のアニメは海外で大きな成果を上げていますが、実写映画の存在感は低い。私が映画界に入った60~70年前は、黒澤明、小津安二郎、溝口健二らが世界に名を残す作品を生み、日本はアジアの映画先進国でした。今は韓国や中国の躍進がめざましい。日本も映画を文化産業として、国が本気で支援してほしい」と訴えた。