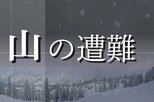2024年も残りわずかとなった。新潟県内ではこの1年、能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。やコメの品薄が暮らしを動揺させた一方、「佐渡島(さど)の金山「相川鶴子金銀山」と「西三川砂金山」の二つの鉱山遺跡で構成。17世紀には世界最大級の金の産出量を誇った。金の採取から精錬までを手工業で行っていた時代の遺構が残っているのは、世界的に例が少ないとされる。」の世界文化遺産1975年に発効した世界遺産条約に基づき、歴史的建造物や遺跡を対象にユネスコが人類共通の財産として登録する。国内では姫路城などが登録されている。世界遺産にはほかに、貴重な生態系などの自然遺産と、文化と自然の要素を併せ持つ複合遺産がある。登録の可否は世界遺産委員会が決める。登録やパリ五輪での県勢の活躍が県民を沸かせた。ニュースの現場を駆け回った記者の視点で振り返る。(3回続きの1)
◆[能登半島地震]真綿で首を絞めるように…液状化被害の厄介さ痛感
「こっちではなく、そちらに座ってください」。能登半島地震で液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。被害に苦しむ新潟市西区の女性宅に伺った時だった。何げない会話だと思ったが、女性は「斜めになった家では、見下ろすような位置のそちらが楽。だから、そちらにどうぞ」と続けた。取材で自宅に上がらせてもらっていただけに、予想もしない気遣いに申し訳ない思いがした。
元日の地震では、新潟市西区...