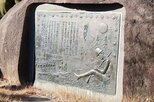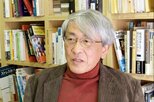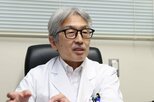室町時代に観阿弥、世阿弥親子が大成した能。芝居や舞踊、声楽、装束、歴史といった日本文化が詰まった「総合芸術」と評される。織田信長や徳川家康ら戦国武将も愛したという。
ただ、能と聞くと、「難しそう」「分かりにくい」と思う人も多いのでは。筆者もずっとそう感じてきた一人。母が趣味で能を舞っていたが、高尚すぎて近づけないといったイメージは拭えず、舞台で能を見たことはなかった。
最近、母が体調を崩し能をできなくなった。家ではいつも、扇子を手に舞ってみたり、何を言っているか分からない歌のようなものを歌ってみたり…。理解はできなかったが、母が熱心に稽古する姿が印象に残っている。
母を引きつけた能の魅力は何だろう。初心者向けの能の公演があると聞き、新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあにある能楽堂を訪ねた。
解説を聞きながら初めて能を見た。演目は「融(とおる)」。光源氏のモデルとされる源融(みなもとのとおる)の亡霊が過去の栄華に思いをはせながら、月に照らされて踊る場面だった。
能は主役が幽霊で、あの世とこの世をつなぎ、生前のうらみを語るパターンが多い。融もそうだ。
短い場面でも1時間以上かけて演じる。シテと呼ばれる主人公の舞は静かに、時に力強い。バックコーラスのような「地謡(じうたい)」は独特のリズムで、ゆらぎを感じて耳に心地よかった。

鑑賞している間、時の流れがゆっくりに感じた。慌ただしい日々の中、時空を超えて夢とうつつを行き来しているようで、静かな空間で心も浄化された。
「幽玄」と呼ばれる能の世界に誘われ、身構えない楽しみ方を学んだ。...
残り2875文字(全文:3544文字)