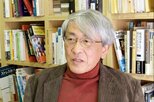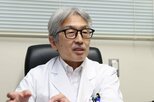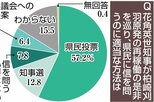「おせっかい」と聞くと、どんなイメージを持つだろうか。
新潟県民に聞いて回ったところ、「大阪のおばちゃんが思い浮かぶ」と笑って答えた人がいた。一方で自らのことを「新潟の人はおせっかいはしないかも」と言う人も。「頼まれたらそれ以上のことをするが、頼まれないとしない。よく言えばわきまえているが、人の目を気にして出しゃばりたくないところがある」と県民性を分析する人もいた。
大阪府出身の筆者は、おせっかいが当たり前の環境で育った。
雨の日の登校時には、車で通りかかった知人から「乗って行き!」と声がかかるし、町角で地図を見ようものなら、「どこ行きたいんや?」と誰かがすぐに聞いてくる。とっさに声が出たというくらいの自然体で、友人知人、見ず知らずの人からのおせっかいが、日常にあふれていた。
そのせいだろうか。自身もいつの間にか同じような行動をするようになってきたようだ。だが、大阪を離れた現在では、「余計なお世話かな」とためらうことも多い。
新潟市西区を中心に活動する傾聴ボランティア陽だまりの代表、冨岡五子さん(77)の言葉、「おせっかいは大事な対話の一つ。でも、『あなたのためを思って』は自己満足」は、肝に銘じたいところだ。
「おせっかい」を会の名前に掲げて活動する人たちもいる。今回、東京や新潟の3団体に話を聞いた。
そのうちの一つ、一般社団法人「おせっかい協会」会長の高橋恵さん(81)=東京都=は、会のことを「皆いい仲間なんですよ。利他の心で、損得関係なく行動している」と穏やかな表情で語っていた。それは他の2団体にも共通しているように思う。
いずれも10年ほどの活動歴を持ち、縛りも会費もなく、メンバーそれぞれの自主性で成り立っている。利他の心を持ち、他者に寄り添い、損得抜きで動いているからこそ、周囲から認められ、仲間が集まってくるのだろう。彼らのおせっかい活動を紹介したい。...