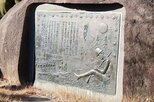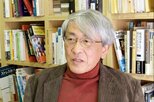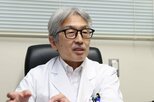伝統的な日本家屋「妻入り」の家々が連なる新潟県出雲崎町の海岸沿い。町を歩くと、街並みや家屋が描かれたスケッチ画の看板をあちこちで見かける。手掛けたのは東京芸術大学の大学院生だ。毎夏、スケッチ合宿で町を訪れ、作品を残していく。町民の発案で始まった合宿は2024年で38年となった。合宿の歴史や先人の歩みを探り、妻入りの街並みが結んだ画家たちと町との交流をたどった。
(柏崎総局・鈴木啓予)
“日本一長い”街並みをキャンバスに…町民の熱意が生んだ交流
合宿10周年画集に記された“起点”
出雲崎町の観光名所「妻入りの街並み」は、間口が狭く奥行きが長い「妻入り」の造りの家屋が尼瀬から井鼻まで連なる。範囲は3・6キロに及び、日本一の長さとされる。この地に、町民有志が東京芸術大のスケッチ合宿を呼び込んだのは1987年のことだ。
いきさつは、合宿10周年を機に町が発刊した画集に詳しい。画集によると87年、東京芸大の職員が町を訪れた。その際、地域の歴史と文化を守る活動をしていた町民団体「出雲崎街並活性研究会」のメンバーと出会う。

職員と酒を酌み交わす中で、研究会の会長だった鈴木豊吉さん(2002年に77歳で死去)らが「街並みを絵に残してほしい」と学生のスケッチ合宿を提案した。研究者から「約4キロも続く妻入りの街並みは全国的にも珍しく、貴重だ」と聞いていたメンバーの熱意は強く、「合宿費用は地元が出す」と掛け合った。
大学に戻った職員は、当時日本画科の主任教授で、後に学長も務めた故平山郁夫さんに相談する。「作品を地元に残すのであれば、参加者は大学院生に限ること」を条件に、合宿の実施が決まった。合宿に当初から携わった町民は「より良い作品を残そうと、学生ではなく院生を参加させたのではないか」と推察する。
町民は、院生たちを歓待した。とりわけ、合宿を提案した鈴木さんと妻の故吉江さんは中心的な役割を果たし、自宅に院生を受け入れ続けた。

2024年に92歳で死去した吉江さんに代わり、娘の目﨑かよ子さん(64)は言う。「父はこの町が大好きで、どうやって町の良さを残そうかと、いつも考えていた。母は父が亡くなっても、20周年まではなんとか続けようと、院生を受け入れてきた」
鈴木さんと共に約20年、合宿に携わった出雲崎町尼瀬の佐藤昭四郎さん(95)も「鈴木さん夫妻のご尽力がなければ、ここまで続かなかっただろう」と振り返る。佐藤さんは、町を訪れた芸大生と今も年賀状のやりとりをしており、アルバムやもらった絵は自宅で大切に保管している。
町によると、終了の危機もあった。大学側が2008年、...