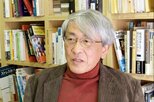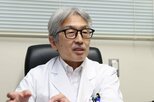新潟清酒好きがそわそわし始める季節がやって来る。そう、毎年3月に行われる「にいがた酒の陣」のことだ。「早すぎだ」とツッコむことなかれ。年明けにはチケットが売り出される。前回は1時間ほどで売り切れた日程もあるほどだ。新型コロナウイルス禍での中止を経て、23年3月、4年ぶりに再開。18回目となる次回は25年3月8、9の両日に開かれることが近頃、主催者から発表された。入場者数は前回に比べ2日間で2000人増やし、計1万8千人とする。多くの左党が待ち焦がれるイベントの歩みや魅力を探ってみた。
ビールの祭典に着想、感染禍を経て「あるべき姿」に
2004年の第1回開催、盛況ゆえの苦悩…そして転機
そもそも、「にいがた酒の陣」は、県酒造組合が2004年に創設50年となるのを記念した、1回きりのイベントの予定だったという。
50周年事業のヒントを得ようと03年、若手蔵元中心でヨーロッパを視察した中、ドイツ・ミュンヘンで行われている世界最大のビールの祭典「オクトーバーフェスト」に訪れた。
大きな会場で大勢の人々がビアジョッキを傾け、談笑していた。前回までの「にいがた酒の陣」実行委員長で、視察にも参加した麒麟山酒造代表の斎藤俊太郎さん(57)は振り返る。「刺激を受けました。ビールと日本酒、ものは違えど、同じアルコール。日本酒でもこれほど人が集まり、誰もが盛り上がれるイベントをやってみたい」

そして朱鷺メッセという会場が新潟にできたばかりだったこともあり、メンバーの中で徐々にイメージが膨らんでいった。
それまでのイベントは、蔵元の酒を組合が預かり、来場者に試飲や販売を行うというスタイルだった。50周年はこれまでとは異なる取り組みにも挑戦した。それは、現在も続く、県内の各蔵元がブースで接客するというものだった。
何人来場するか、どんなオペレーションになるのか、どれほど酒を振る舞うのかも、すべてが未知数だった。それでも「蔵元の顔が見えるイベントにしたい。一度だけでも蔵の思いを知ってもらえる貴重な場をみんなでつくりませんか、とお願いしました」と斎藤さんは話す。
多くの蔵元が賛同して04年に行われた、初の酒の陣には4万9千人超が来場。大盛況のうちに幕を下ろした。

反響の中には翌年の開催も願う声が多数あり、行政からは後押しの申し出もあった。その声に応え、酒の陣は新潟の3月の風物詩となっていった。
東日本大震災の11年を除き毎年開催され、最大来場者数14万人を誇るまでに成長した。イベントに変化をもたらしたのは、...