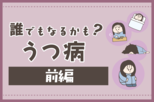「すてる」から考えるデザインで循環型社会を実現する、学生との新たな挑戦
株式会社LIXIL(以下LIXIL)は、多摩美術大学との「未来の窓」創出プロジェクトについてストーリーを公開します。
LIXIL)は、資源循環を促進する窓やドアなどの建材製品アイデアの創出を目指し、多摩美術大学との産学共同プロジェクトを2024年10月〜2025年8月に実施し、既存の枠を超えた機能や新しい価値について検討しました。
[画像1]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/700_585_2025102818130769008923ec46f.png
この活動は、環境負荷を低減するLIXILの窓「GREEN WINDOW※1」と、多摩美術大学が推進する「すてるデザイン※2」という二つの考え方を融合させ、資源循環を促進する新たな製品アイデアの創出を目指すものです。「Cassettable ~ 窓とドアのこれから ※3」をコンセプトに、既存の窓やドアに新たな付加価値を与える、未来の形を探りました。
プロジェクトは、学生一人ひとりが自身の興味に基づき「窓・ドア」のテーマを深掘りすることから始まりました。窓とドアの「構造」や「あり方」の可能性を広げるため、自然界の仕組みや身近な事象からリサーチを重ね、LIXILの開発・技術研究所・デザインに携わるプロジェクトメンバーとの議論を通じて、求められる新たな価値を具体的なアイデアとモックアップに落とし込みました。集大成として2025年9月には、LIXILの品川ラボで最終評価会を実施し、学生代表が活動の成果を発表しました。
今回の取り組みを通じて、新しい視点からのプロダクト提案だけに留まらず、多摩美術大学のデザインプロセス、そして将来のユーザーとなる学生たちの価値観やサステナビリティへの視点を通して、窓・ドアが単に住宅を構成するパーツという従来の役割を超え、「住む人が自然や社会とつながる接点」としての新たな価値をエコシステム全体で実現し、持続可能な社会や暮らしに貢献していく未来を予感させるプロジェクトとなりました。
※1 LIXILが提唱する、省エネルギーと資源循環を実現する地域に最適な窓の総称。詳細はこちら(https://www.lixil.co.jp/lineup/window/greenwindow/
)
※2 “つくる”ことで産業を⽀えてきたこれまでのデザインから、“すてる”を考えることでデザインを切り口に循環型社会へアプローチする共創プログラム。詳細はこちら(https://tub.tamabi.ac.jp/projects/1265/)
※3 窓やドアをCassetto(引き出し)のように交換利用することで広がる価値創出のコンセプト
[画像2]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/350_233_202510281813166900892c58ebb.jpg
[画像3]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/350_233_20251028181325690089354e8cb.jpg
[画像4]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/350_233_202510281813336900893de53e8.jpg
[画像5]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/350_233_2025102818135469008952b25a6.jpg
2025年9月にLIIXLの品川ラボで行われた最終評価会の様子
また最終評価会を終え、プロジェクトを担当したLIXILのサッシ・ドア事業部 商品開発室の宇山健と多摩美術大学生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻の濱田芳治教授、そして両者の仲介役を果たした合作株式会社の代表取締役 齊藤智彦氏の三者が思い描く「未来の窓」について語りました。
[画像6]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/600_399_202510281814036900895ba1e0c.jpg
(左から)多摩美術大学濱田芳治教授、LIXIL宇山健、合作株式会社齊藤智彦氏
自由に取り外せる窓を想定し、窓やドアの新たな価値を創る
――今回のプロジェクトの概要と、多摩美術大学とLIXILが共創することになった経緯について教えてください。
宇山:LIXILでは以前より、環境負荷を低減する地域に最適な窓を「GREEN WINDOW」と宣言して、さまざまな製品を展開してきました。そこからさらに高いレベルの循環型社会を実現するためには、製品単体ではなくエコシステム全体を捉え、環境戦略との融合が大切になると感じていました。けれども、私たちはずっと窓について考えてきたので、従来の窓の概念から抜け出せずにいたんです。
そこで、新しい視点を増やすために「すてるデザイン」を提唱されている多摩美術大学、環境への取り組みに力を入れている合作社と連携することで、新しいヒントが得られると考え共創することになりました。
――「Cassettable」というコンセプトはどのように生まれたのでしょうか?
濱田:「Cassettable」というコンセプトは、私たち多摩美術大学から提案させていただきました。窓やドアは建物の形で大枠が決まってしまう性質を持つため、学生からすると柔軟な発想をしていくことが難しいんです。特に市販されている窓やドアをリサーチして正解を考えようとする勉強のできるタイプの学生ほど、この傾向が強くなります。プロダクトデザインという分野では、開発に際して前提条件がいろいろと設定されることが多いため、クリエイターとして一から創り上げていく力を発揮するというよりも、既存する問題の解決のためにパズルを解くことが主になりがちです。「Cassettable」というコンセプトでは、カセットを替えると音楽が変わるように自由に取り外せる窓を想定しています。それくらい従来の窓とは異なる視点を提示することで、クリエイターの創造する力が発揮しやすくなると考えています。
社会が窓やドアに与える影響を考え、一からそのあり方を見直す
――LIXILと多摩美術大学の仲介役を果たした合作株式会社の齊藤さんに伺いますが、どのような意図で両者をつないだのでしょうか?
齊藤:僕らは鹿児島県の大崎町という資源リサイクルが高い自治体を拠点にして、世界のモデルになるような循環型の街をつくるべく活動をしています。循環型の街をつくるためには一つの地域だけではなく、企業や研究機関などと連携を生み出す必要があるので、僕らはそういった連携のコーディネートも手がけています。多摩美の「すてるデザイン」の活動については以前から知っていて、何かご一緒したいと考えていたところにお声がけいただき、大崎町で取り組みを進めてきました。同時期にLIXILからも「循環型社会やサーキュラーエコノミー(循環型経済)での知見を貸してほしい」というご相談があり、LIXILの社内だけでは閉塞感があって新しいアイデアが広がっていかないという課題を共有いただきました。そこで、アイデア出しからプロトタイプの制作まで可能な多摩美の学生をおつなぎすることで、課題解決ができると考えました。
自然環境から家を守り、外部とのつながりを開く窓
――今回の共創は学生にとってどのような影響がありましたか?
濱田:長期に渡るプロジェクトの中で何回も繰り返しアイデアを練ったことが、学生にとってとても良い経験になったと思います。ただ、何回もアイデアを出すだけですとアイデアは広がる一方になるため、最終提案に向けてプロトタイプ化を意識してアイデアを集約し、具体化していきました。そうしたプロセスを経ることで、学生たちの思考を深められた点は、特に有意義でした。
プロダクトデザインは、社会への貢献が求められる分野です。それはいわゆるクリエイターの自己表現とは少し性質が異なります。自分のやりたいことをやるだけではなく、自分は社会に対して何ができるのかを考えることが大事になります。自己表現を重視している学生に対して、客観的な視点を持たせ、社会に対する意識を醸成するという点で、こうした産学共同プロジェクトは非常に有効な学びの機会になると考えています。
[画像7]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/600_323_202510281814066900895edb23b.png
製品アイデアについて意見交換をする多摩美術大学生とLIXILのプロジェクトメンバー
――本プロジェクトに参画して得た知見や、期待していることを教えてください。
齊藤:これまでもサーキュラーエコノミーを生み出すための挑戦を続けてきましたが、多くの企業から「環境性能を高めた商品をつくっても売れない」という声を耳にします。僕はここに環境性能を追い求める罠があると感じています。今回の取り組みを通じてわかったのは、人々は環境性能の高い商品よりも、日々の豊かな生活へのニーズが高いということでした。環境性能を追い求めた商品は、人々の生活を踏まえたものづくりがあって初めて訴求できるものです。
もう一点、日本の美大に対する考えなのですが、海外に比べて日本の美大は単科大学が中心で、総合大学の中に含まれている事例は少ないのが現状です。それは、美術や創造性の持つ価値が限定され閉鎖的になってしまうのでもったいないと感じます。今回のような産学共同プロジェクトに学生が参加することでそれらの価値が世の中に循環していくし、何より学生にとって大人たちの考えや発想に触れることは良い経験になると思います。
[画像8]https://digitalpr.jp/simg/2979/121312/600_399_20251028181417690089691b641.JPG
――多摩美術大学が掲げる「すてるデザイン」から考える未来の窓とはどのようなものでしょうか?
濱田:私たちのアプローチでは、まず「未来の窓」や「未来の暮らし」を思い描き、その中で窓やドアはどんなことができるのかを探っていきます。未来の窓やドアに求められるのは、外部とのつながりをどのようにつくっていくか、そういう役割だと思います。地球温暖化の影響が避けられないこれからの時代、雨は激甚化して河川の氾濫は多くなるでしょうし、台風もより強力になるでしょう。日照も厳しくなるので、これらの環境変化から家を守る、人を守る機能が窓やドアには必須になります。その上で人と人、人と自然をどうつないでいくか。それが私たちの考える「未来の窓」だと考えています。
――そのような未来の窓について、LIXILとしてどのように向き合っていくのか教えてください。
宇山:今回の取り組みによって、窓の捉え方に新しい視点や気づきをもたらしていただきました。窓のあり方について改めて考える機会となり、人と窓のつながり、社会と窓のつながりはとても大きいものだと実感しています。窓の性能やデザイン性を高め、顧客ニーズを取り込むことも重要ですが、「人々の生活を豊かにする窓」という視点も欠かせません。その視点がないまま環境性能を高めたプロダクトを一方的につくるのではなく、サーキュラーエコノミー、循環型社会の実現につながる窓が未来の窓の形だと考えています。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL(証券コード: 5938)は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト:https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
GREEN WINDOW
https://www.lixil.co.jp/lineup/window/greenwindow/
すてるデザイン
https://tub.tamabi.ac.jp/projects/1265/
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/