
世界文化遺産を目指す「佐渡島(さど)の金山「相川鶴子金銀山」と「西三川砂金山」の二つの鉱山遺跡で構成。17世紀には世界最大級の金の産出量を誇った。金の採取から精錬までを手工業で行っていた時代の遺構が残っているのは、世界的に例が少ないとされる。」は、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の委員会で7月末に審議される。いよいよ登録に向けた最終段階に入ったが、新潟県は広い。佐渡以外の県民の中にはピンとこない人もいるだろう。しかし島外にも、佐渡金山とのつながりを示す史料や伝承が残っている。県内各地で見つけた佐渡金山との意外な縁を紹介する。(5回続きの2)
江戸時代後期の開発当初は鉛を採掘していたが、佐渡との縁がきっかけとなって銀を生産するようになったとされるのが、三条市下田地区にあった拾石(じっこく)銀山だ。
下田村史によると、拾石銀山の歴史は鉛の採掘から始まる。鉛石の発見を機に、地元住民が1827(文政10)年に採掘を開始。翌年には初の製錬で412キロの鉛が得られたとされる。
転機は3年後。金鉱石から金を取り出すために佐渡奉行所に納められた鉛の中に、銀が多く含まれていたことが分かった。31(天保2)年には銀を製錬するための職人が金銀山で栄える佐渡・相川から招かれ、34貫(約127キロ)の銀が得られたという。
地元の歴史に詳しい渡辺隆一さん(81)=三条市八木前=は「地元でも佐渡とのつながりを知らない人は多い。佐渡の人が銀に詳しかったからこそ、この地域でも本格的に銀が取れるようになったと言えるのではないか」と語る。
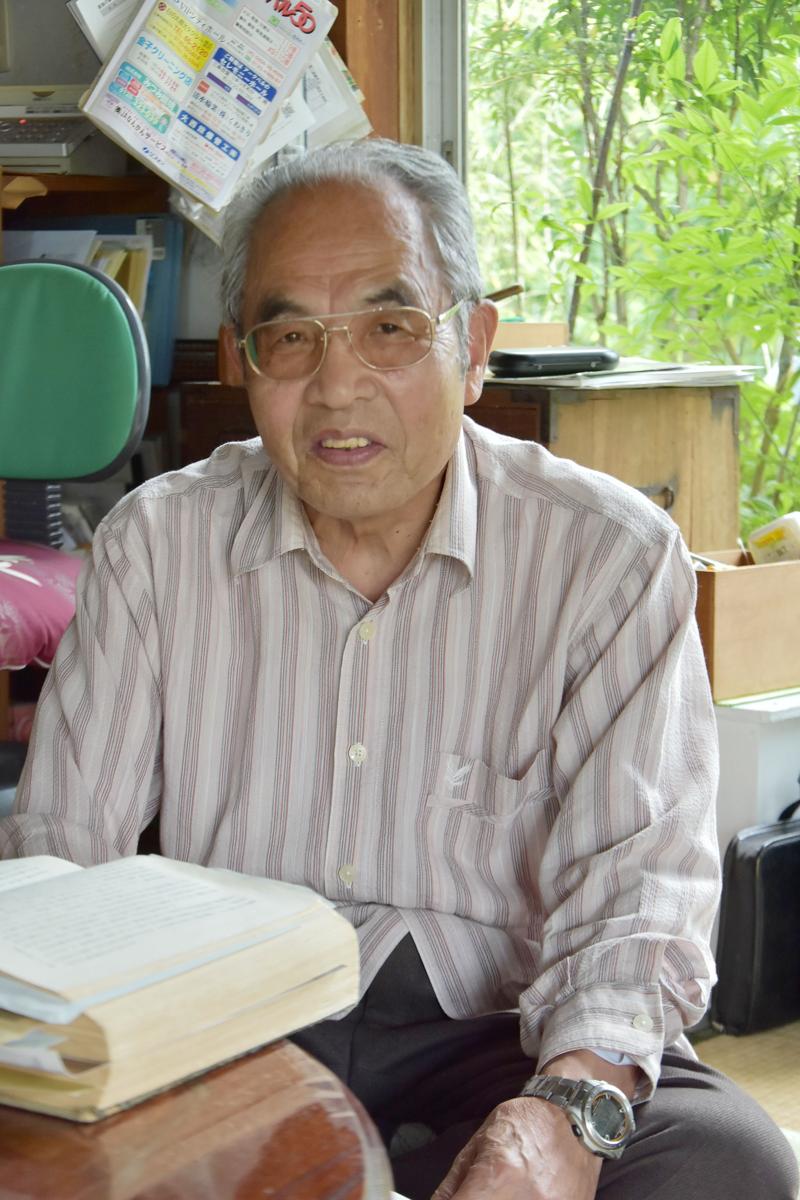
その後、3年ほどは年間30貫以上の生産量を保った...
残り1925文字(全文:2512文字)











