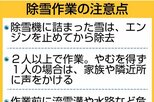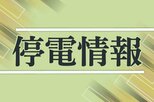水俣病熊本県で1956年に公式確認された病気で、その後、新潟県の阿賀野川流域でも集団発生した。毒性の強いメチル水銀を含む工場排水で汚染された魚介類を食べた人やその胎児が水銀中毒を発症し、亡くなった人も多い。症状は感覚障害や運動失調、視野狭窄(きょうさく)など。外見的な異常は現れずとも、手足のしびれや頭痛などに悩まされ続ける人もいる。特有の症状がありながら患者認定を棄却されたとして、新潟市と新潟県阿賀野市の男女8人が県と新潟市を相手取り、棄却の取り消しと認定義務付けを求めた新潟水俣病1965年、新潟県の阿賀野川流域で公式確認された。阿賀野川上流の鹿瀬町(現阿賀町)にあった昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)の鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産過程で生じたメチル水銀を含む排水を川に流し、汚染された川魚を食べた流域住民が、手足の感覚障害や運動失調などを発症する例が相次いだ。56年に熊本県で公式確認された水俣病に続く「第2の水俣病」と呼ばれる。第2次行政認定訴訟感覚障害など水俣病特有の症状がありながら患者認定を棄却された被害者が、認定業務を行う新潟県や新潟市に棄却処分の取り消しと患者認定の義務付けを求めた訴訟。新潟市を相手取った新潟水俣病第1次行政認定訴訟では、2017年11月に東京高裁が原告9人全員を水俣病と認めるよう新潟市に命じた。新潟市は上告せず判決が確定し、9人を水俣病患者として認定した。の原告本人尋問が10月31日、新潟地裁(鈴木雄輔裁判長)で始まった。阿賀野市の70代男性が自身や母について、阿賀野川の魚を日常的に食べていたことや、視野狭窄(きょうさく)や耳鳴りなどの症状を証言した。本人尋問は同訴訟で初。
- 原告の症状変化「一般的にない」と被告側証人の神経内科医 確定診断の基準「詳しく知らない」とも
- 原告の症状「四肢ともに障害、糖尿病ではあり得ない」原告主治医が水俣病と主張
- 水俣病の症状は変動しないと被告側主張、原告主治医「(症状の変化は)当然予想されること」
- 新潟水俣病第2次行政認定訴訟、証人尋問始まる・新潟地裁 主治医「原告8人全員に水俣病と認定できる症状ある」と証言
男性の父はしびれなどで、公害健康被害補償法に基づく認定患者だった。
男性は主尋問で、父が捕ってきた川魚を幼少期からほぼ毎日食べていたと説明。「子どもの頃は物流手段もなく、川魚は大事なタンパク源だった...