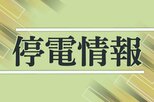蒸したコメでこうじを造る八海醸造の蔵人=12月5日、南魚沼市長森
日本の「伝統的酒造り」が日本時間12月5日、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産2006年発効の無形文化遺産保護条約に基づいて国連教育科学文化機関(ユネスコ)が登録する無形の文化。伝統芸能や工芸技術、祭礼行事など多岐にわたる。183の締約国から選ばれた24カ国で構成する政府間委員会が毎年1回、評価機関の勧告を踏まえて登録の可否を決める。文化の多様性を示していることや、国内の保護措置が取られていることなどが登録の条件。新規の審査上限は年60件程度で、日本など件数の多い国は実質2年に1回の審査となっている。に登録された。日本酒の製造が盛んな新潟県内では、関係者が伝統の継承や新潟清酒のさらなる振興へ思いを強くしている。
新潟県は日本酒の酒蔵数が日本一で、県酒造組合(新潟市中央区)には90蔵が加盟する(2023年末時点)。
新潟県内の蔵元では寒さが厳しくなった12月に入り、酒造りが本格化してきた。「八海山」で知られる八海醸造(南魚沼市)は12月5日、酒造りで重要なこうじを造る作業などを行った。
八海醸造は以前から...
残り604文字(全文:881文字)