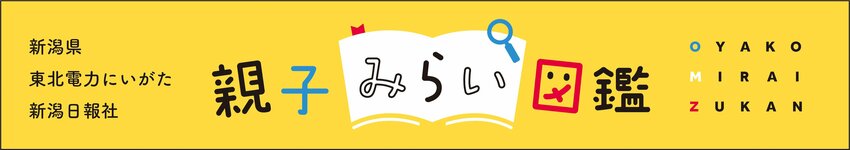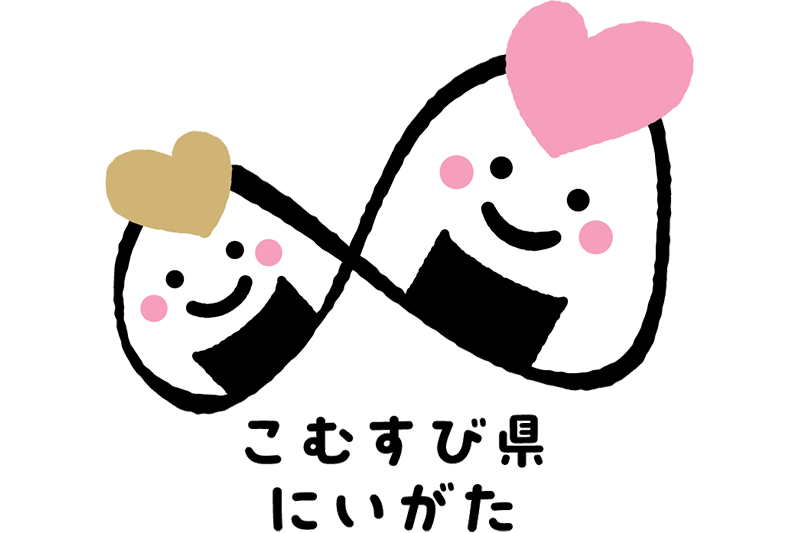
新潟県内では企業や自治体が、子育てを応援するさまざまな取り組みを行っています。この特集では、子育て環境の改善やこどもたちが過ごす社会を良くするための事例などを紹介。子育て環境がより良い形で整っていくことで、みんなが笑顔で過ごせる新潟の“みらい”が見えてきます。
新潟県福祉保健部こども家庭課こども政策室/政策企画員 水野学さん
新潟県福祉保健部こども家庭課でこども政策、子育て支援、結婚支援などを担当。自身も3人の子を持つ親。

Q.「新潟県こども条例」が出来たきっかけを教えてください
A.当たり前の話なのですが、こどもは一人一人がとても大切な存在です。こどもたちが自分らしく、元気に育っていくことは、県民の皆さんの願いだと思います。県も「こどもたちが安心して成長できる社会をつくりたい」という思いから、この条例をつくりました。条例を通じて、県の考え方や目指す方向をはっきりさせ、県民のみなさんと一緒に、こどもを支える環境をもっと良くしていきたいと考えています。
Q.条例におけるポイントを教えてください
A.こども条例では、「こどもの権利を守る」「こどもの意見を大切にする」「新潟県のみんなでこどもを支える」という3つのポイントがあります。このうち、2つ目のこどもの意見を大切にするという点では、条例を作る過程で、保育園や学校等に私たちが直接出向き、園児から大学生まで約100人のこどもたちと対面で意見の聴き取りを行いました。さらに、小学生から20代の若者までを対象とした「こどもパブリックコメント」を行い、こどもや若者の皆さんの意見が300件近く集まりました。こどもたちから聴いた意見の中で、実際に条例案に反映したものもあります。

Q.条例を受けて大人が意識するべきことは?
A.新潟県こども条例はこどもだけでなく、こどもの周りにいる大人、そして直接子育てには関わっていない皆さんも含めて、社会全体でこどもたちを支えていこう、というものです。こどもたちの意見の中には、「悩んだときに相談しやすい大人がいてくれるといい」、「私たちも意見を持っているので、大人も私たちの話をちゃんと聞いてほしい」という声もありました。県民それぞれに自分事として、「こどもを支える、見守る」ということを考えていただきたいですね。
Q.条例を施行し、今後はどうなっていきますか?
A.現在、こども条例に基づいて、具体的な取り組みを記載する「新潟県こども計画」を作っています。条例というのはあくまでメッセージというか、理念のような存在なので、それを基に令和6年度中に計画を策定し、来年度から実行していくことになります。ぜひ県民の皆さまにも参画していただき、社会全体でこどもたちを応援していっていただきたいと思います。

「全ての県民がこどもの声に耳を傾けられる社会を目指しています」と水野さん