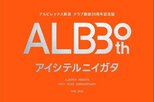ちょうど今日から10年前の2015年9月2日、アルビレックス新潟(アルビレオ新潟)の初代監督、フランス・ファン・バルコム氏が74年の生涯を閉じた。かつて「不毛の地」と言われた新潟に、サッカーの文化を根付かせた功労者の1人だ。ただ、当時を知らない世代の新潟サポーターも多くなった。そしてアルビが苦境の今だからこそ、思い返したい言葉もある。バルコム氏自身も語っていた。「サポーターがいなければ、私たちは上には昇っていけないのです。サポーターはいわば“血”なのです」。熱き血を受け継ぎ、彼の功績について振り返りたい。(以下、敬称略)
「フットボールのスタイルは、勝つか負けるかの二通りしかない」
1994年3月23日、見慣れないオランダ人が新潟県庁に姿を現した。「日本サッカーの問題点は若い選手を育てられないことにある」「フットボールのスタイルは昔はブラジル流などといったが、今は勝つか負けるかの二通りしかない」「新潟のチームを3年でJリーグに入れたい」。バルコムが記者会見で次々に繰り出す言葉を、聞いていた人はどれほど本気で受け止めただろうか。
当時2002年のワールドカップ(W杯)招致を目指していた県が、競技力向上のために招いたのがバルコムだった。チームの育成のほか、小中学生への普及、国体チームの指導なども任される「県サッカー界」全体のコーチを任された。
W杯でほかの国内立候補地にはJリーグチームやJFLチームがあるのに、新潟にあったのは北信越の地域リーグを戦っていた新潟イレブン。もともと新潟明訓高のOBが中心のクラブで、教員に銀行マン、パン屋もいた「サッカー好きの集まり」だ。選手は仕事とサッカーを両立しており、練習は週3、4回ほど。整備された芝生の練習場などあるわけがなかった。

長谷川義明・新潟市長との面会では「新潟市にもしJリーグクラブができたら、毎週4、5万人の観客を集められる」とも語った。今でこそ実際4万人を集めたことは周知の事実だが、それは10年先の話。バルコム初采配の北信越リーグ初戦、鳥屋野球技場に集まった観客は150人だった。
半信半疑の周囲と、土ぼこり舞うグラウンドから始まった挑戦。初練習の際、バルコムは選手たちに語りかけた。「まず自分自身を信じること。フィールド上では選手自身が問題を解決しなければならない」。不毛の地に種をまく、最初の言葉だった。

「おかげで日本代表になりましたからね」(松木安太郎)
そもそもバルコムは、アルビだけのレジェンド的存在ではない。
現役選手を引退した後、「日本サッカーの父」とも言われるデットマール・クラマーに...