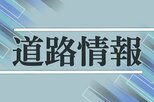水鳥が生息する国際的に重要な湿地であるとして、ラムサール条約に登録されている佐潟(新潟市西区)。冬にはコハクチョウやマガモなど野鳥が数多く飛来する砂丘湖だ。夏には湖面いっぱいにハスが桃色の花を咲かせていたが、2018年にハスが消失して以降、その光景は見られなくなった。市民有志は「佐潟の夏を取り戻そう」と、ハスなどの水生植物を食い荒らしている外来種のカメの捕獲に取り組んでいる。(運動部・森田雅之)
「仕掛けが重いぞ」。7月下旬、額に大粒の汗を浮かべながら、新潟市西区赤塚出身の飯田武さん(45)が、仲間とともに水面に仕掛けたカメ捕獲用のわなを引き揚げた。かごの中には10匹近いカメがうごめく。捕獲したカメを大きな桶(おけ)に入れると、「メス、19センチ、1360グラム」などと、慣れた手つきで次々と大きさなどの情報を記録した。
この日は、環境問題や生物に関心を寄せる高校生2人も同行。飯田さんらは雌雄や種類の見分け方、カメの生態などを説明しながら、約3時間かけて17個のわなを引き揚げた。
新潟市からカメの駆除を委託された業者からの依頼を受け、飯田さんらは24年度にカメ用わな10個を仕掛けた。すると、約70日間でアカミミガメ545匹、クサガメ464匹を捕獲。25年度は仕掛けを17個に増やし、約70日間でアカミミガメ1104匹、クサガメ863匹を捕獲した。

市環境政策課は、これまでの捕獲調査により、繁殖して数を増やしたカメが水生植物を食い荒らす「食害」が、ハス消失の一因とみている。飯田さんは、捕獲後にカメが吐き出す内容物を確認すると「8、9割が水生植物だ」と語る。
捕獲したカメのうち、23年に「条件付特定外来生物」に指定されたアカミミガメは冷凍して安楽死させた後、米ぬかやもみ殻と混ぜて堆肥にしている。飯田さんは「外来種は悪者ではない。しかし、より多くの生物の命を守るために、命を奪わなければならない」と考え、カメの命を無駄にしないよう、堆肥を使った野菜作りにも取り組んでいるという。
佐潟のアカミミガメ生息数は数万匹に上るともされ、わなにかかる数は一向に減らない。飯田さんは景観だけでなく、生態系への悪影響を案じる。ハスなどの水生植物は、水生生物が産卵する場でもあり、鳥類などが水生生物を食べることから、「命を次につなげられなくなり、生物の多様性が損なわれる。実感では、今夏はトンボが激減している」と表情を曇らせる。

ハスの復活に向けては、地元住民や子どもたちがハスを育てる取り組みを進めている。飯田さんも、取り組みに関心を寄せる若者を積極的に受け入れ、自然や命の大切さを伝えている。
緑一つない湖面を前に、飯田さんは「何十年かかるか分からないが、ハスが広がる光景をもう一度見たい。未来を背負う子どもたちにも、この問題を通じ、自然や命について理解を深めてもらいたい」と語った。...