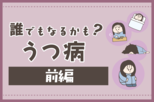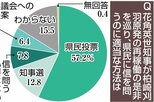能登半島地震で稼働する静岡県富士市のトイレトレーラー(富士市提供)
大規模災害が起きるたび、被災者はトイレの不足に苦しんできた。平時には当たり前と思える存在がひとたび失われれば、体調は悪化し、災害関連死の引き金ともなる。自治体は予算や保管場所といった壁に直面。量と質をいかに確保するか、試行錯誤が続く。
▽危機意識
汚物があふれた便器。雪の中、仮設トイレへ通う高齢者。断水は水洗トイレの使用を阻む。昨年1月、能登半島地震で見られた光景だ。
緊急支援チームの一員として石川県珠洲市の避難所へ入った看護師木下真由香さんは「頻度を減らそうと水分摂取を控える人や落ち着いてできずに便秘で悩む人が多かった」と振り返る。
NPO法人「日本トイレ研究所」によると、仮設トイレを地震...
残り1021文字(全文:1321文字)