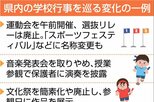新型コロナウイルスの流行「第7波」の感染拡大が続く中、一部の専門家から「低リスクの軽症者は自宅療養」や「感染者の全数把握の見直し」などの意見が出ている。新潟日報社の「もっとあなたに特別報道班」(もあ特)の会員に医療態勢や対策の緩和について聞いたところ、さまざまな意見が寄せられた。(報道部・黒島亮)
約60人の会員から意見が寄せられた。軽症者の自宅療養については、医療機関が逼迫(ひっぱく)していることから「(軽症の人も病院へ行くと)持病のある人や特に体調の悪い人が行けなくなる」(新潟市西区、60代男性)、「大切なことは必要な人が必要なときに医療が受けられること」(新潟県三条市、70代女性)などとの意見が聞かれた。
一方、「自宅療養は、医療体制の不備の責任を国民に背負わせることだ」(新潟市、60代女性)、「根本的に治療する薬がないのに自宅療養とは無責任」(新潟県佐渡市、70代男性)といった批判もあった。
また、軽症の定義が分からないという戸惑いもみられた。「軽症と判断した人が急変した場合の対策などが完璧になってからでないと、見直しは受け入れられない」(新潟市西区、70代男性)などの意見があった。
感染者の全数把握の見直しには理解を示す声が目立った。50代男性は「全数が公表されてもされなくても、日ごろの感染対策に変わりはない」の意見を寄せた。研究者の待遇改善を含めた治療薬の開発や、保健所の態勢強化のための予算の拡充を国に求める声も出た。
医療関係者からも声が寄せられた。
新潟県央地域の40代看護師は「現場は本当に逼迫している。感染した人がいても診られず、病床もない状況になり、恐怖を感じる」と現状を記し、行政が一括して患者の入院先を管理することなどを求めた。医療機関職員の50代女性は「医療者も救急隊員も保健所職員も長引く対応により疲弊している。医療者も人間」と訴えた。
新型コロナウイルスの感染症法上の扱いを現在の「2類」相当から季節性インフルエンザ並みの「5類」へ変更する案に対しては、下越地方の総合病院で看護師をしている40代女性は「飲み薬ができていない段階での引き下げは危ない。薬の開発を含めて態勢が整ってから変更すればいい」とした。