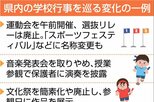◆新潟大大学院の齋藤玲子教授、一定の理解も「感染防止は続けて」
新型コロナウイルスの感染対策について、新潟大大学院医歯学総合研究科の齋藤玲子教授(公衆衛生学)は、低リスクで軽症の人の自宅療養や、全数把握の見直しには一定の理解を示した。その上で、引き続き感染防止を続けるよう呼び掛けた。
齋藤教授は「低リスクで軽症の人は数日間、安静にしていれば治ることが多く、薬についても市販の熱冷ましなどで対応できる場合が多い」と話す。
もあ特会員からは、軽症の定義が分からないと戸惑う声も聞かれた。齋藤教授は、食事が取れない状況になると注意が必要と説明。「食べたり飲んだりができなくなると脱水につながり、点滴で水分を供給しなければならない状態になることがある」とし、医療機関の受診が必要になるとした。呼吸が難しい状況になった場合なども同様だ。
全数把握の見直しについては「患者数を自治体が把握するには多すぎる数になっている」とし、やむを得ない状況と指摘。個々の医療機関が、それぞれが担当している患者数は正確に把握するなどして対応していく必要を説明した。
現状での5類への変更に関しては「感染者が急増している中で対応を変えると混乱が懸念される」とし、慎重な見方をした。
多くの人がマスクの着用など感染防止策を続けている。こうした防止策について、齋藤教授は「もし対応が見直されることになったとしても、感染防止策が要らなくなったということではない。防止策を続けてもらいたい」と話した。