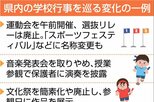1964年6月16日の新潟地震では、新潟県内で少なくとも13人が亡くなった。「当時、新潟地震による死者はいないという情報があった」。そんな疑問を新潟日報の「もっとあなたに特別報道班」(もあ特)で取り上げたところ、もあ特会員から当時耳にしたさまざまな情報が寄せられた。「死者ゼロ」「数十人が犠牲に」…。会員の証言からは地震直後の混乱ぶりがにじむ。(報道部・黒島亮)
もあ特で最初に取り上げたのは6月14日付の新潟面。新潟市中央区の80代男性からの手紙を基に取材を進めたが「死者ゼロ」の事実はなく、一方で県内の犠牲者の数が資料で異なっていることが分かった。
県や新潟市の資料によると、新潟地震の県内の死者は新潟市11人、柏崎市2人、紫雲寺町(現新発田市)1人の計14人。一方、国立研究開発法人「防災科学技術研究所」(茨城県つくば市)の公開データは紫雲寺町がゼロで、死者数は13人となっている。
この記事の掲載後、11人のもあ特会員から新潟地震に関する情報が寄せられた。このうち「死者ゼロ」の情報を聞いたことがある人が2人いた。
その中の一人で、当時小学生だった会員は学校の教員の話をはっきりと覚えている。
「すごい地震が起きたが、新潟県の人たちの適切な判断力と素早い行動力や助け合いの精神で死者はいなかった。新潟県民は素晴らしい」
教員の発言がどのような根拠に基づいていたのかは不明だが、この会員は「小学生ながらに『うそだ』と思って聞いていた。県が県民の団結力を醸し出そうとしたのではないか」と振り返る。
一方、別の会員は「数十人が犠牲になったと聞いた記憶がある」とのコメントを寄せた。
死者が出ていることは震災直後から報道されていた。地震翌日の64年6月17日付の新潟日報朝刊は1面トップ記事で、「県警に入った報告」として、死者9人、行方不明4人と報じている。地震から1年がたった65年6月16日付の新潟日報夕刊は、新潟震災復興祈念大会の模様を伝え、亡くなった14人の冥福を祈ったと報じている。
しかし、県民の中には当時の記憶を鮮明に覚えている人もいる。災害時に根も葉もないデマが広がることは、過去の歴史が物語る。取材を通して正確な情報の提供の必要性を痛感させられた。
◎長岡大学の米山宗久教授(61)=地域福祉論、社会福祉論=の話 災害に限らず、公的機関の情報やデータは行政の各種計画策定の基礎となる。それを基準に民間団体はサービスを提供し、地域住民は相互の支援活動を行う。新潟地震に関しては60年近く前のデータをさかのぼって再検証することは難しいが、地域で困難なことが起きたとき支え合うために何が必要かを把握するためにも、県民には正確なデータを提供することが必要だ。
▽新潟地震での県内の死者
【新潟市】
●女性(60)が落下した梁(はり)の下敷きになり死亡
●女性(55)が建物の下敷きになり死亡
●男児(3)と親=性別、年齢非公表=が建物の下敷きになり死亡
●女性(25)が地割れに落ちて死亡
●男児(6)が崩れた砂丘にのまれ死亡
●女性(70)が避難中の交通事故により死亡
●女性(76)が集団避難中のショックにより死亡
●女性(48)が津波により溺死
●聾学校生徒(14)=性別非公表=が避難中の人波に押し倒され、全身打撲傷により死亡
●男性(31)がアンモニア爆発により窒息死
【柏崎市、紫雲寺町(現新発田市)】
●柏崎市で2人、紫雲寺町で1人が、ショックのため死亡
(新潟市は市公表資料。柏崎市、紫雲寺町はこれまでの新潟日報の記事を基に作成)