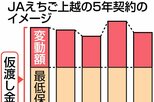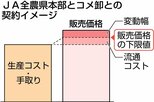2024年産米の出来具合を確認する麓二区生産組合の本多雅志さん=10月11日、弥彦村
農林水産省が10月11日に発表した新潟県の2024年産米の作況指数(9月25日現在)は98と、2年連続で「やや不良」となった。雨による倒伏などにも悩まされ、生産者は収量確保の難しさを指摘する。集荷業者や専門家は、品薄感が解消に向かうかどうか懐疑的な見方を示し、価格も落ち着くかどうか見通せない状況だ。
「今までの栽培技術ではカバーできない段階にきている」。弥彦村の農事組合法人「麓二区生産組合」理事の本多雅志さん(57)は近年の気候変動に対応したコメ作りの難しさを実感している。
約35ヘクタールで5品種のコメを栽培しているが、ことしは早生(わせ)から晩生(おくて)まで、10アール当たり約60キロ収量が落ちた。春の低温の影響は感じていた。多収が見込める品種でも茎の根元から新たな茎が生える「分けつ」が進まず小さい株が多かった。そのため穂も少なかったという。
コシヒカリは7月の日照不足などで背丈が伸び、出穂期直前の追肥のタイミングが難しかったと振り返る。このため気候変動に対応した対策を望む。県は高温耐性がある品種の開発に着手しているが、倒伏しづらいコシの研究開発を求める。
本多さんは大規模化と人手不足を踏まえ、「県全体で一つの対策では追いつかない。各エリアで対策を生産者と行政、JAなどで考える必要がある」と話す。
一方、県内の集荷業者はコメ集めに奔走している。品薄感は徐々に薄れてきたが、中食・外食産業の引き合いが強い中価格帯のコメが特に高騰し、不足して...
残り335文字(全文:985文字)