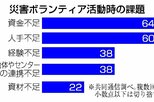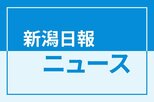1月17日で発生30年となった阪神大震災は、多くの個人ボランティアが活動し、「ボランティア元年」として注目を集めた。震災直後からボランティアとして活動している大阪大大学院の渥美公秀(ともひで)教授(63)=社会心理学=に、この30年間のボランティアの変遷を聞いた。(報道部・平賀貴子)
-阪神大震災におけるボランティアの状況は?
「全国から押し寄せた大勢のボランティアをどう受け止めたかによって、二つの流れができた。臨機応変に活動する様子を肯定的に受け止めた人がいる一方、マッチングがうまくいかず大混乱だと考えた人は、マニュアルを整備し統制する秩序化の方向に動いた。両者はバランスを取って活動してきたが、2024年1月の能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。では、秩序化に大きく傾いた」
-能登半島地震の被災地の現状をどう見ますか。
「石川県は当初、受け入れ体制が整っていないとして来県の自粛を呼びかけ、春になっても取り下げなかった。ボランティアの力を信用していないのか、活動を制限し、単なる労働力として統括しようとした。個人ボランティアが行きにくい状況が長く続き、人手不足は継続している。被災地が失ったことはあまりに多いが、県の対応を責めても仕方ない。行政は行政の仕事に専念するためにも、市民の力を信じてほしい」
-阪神大震災後、ボランティアの役割はどのように変わりましたか。
「ボランティアの受け入れで混乱したとの指摘もあり、ボランティアセンターが設置されるようになった。04年の中越地震2004年10月23日、新潟県中越地方を震源として発生した地震。旧川口町(現在の長岡市)で震度7、旧山古志村、旧小国町(いずれも現長岡市)、小千谷市で震度6強を観測した。新潟県や内閣府の資料によると、地震の影響で68人が亡くなり、4795人が重軽傷を負った。住宅の被害は計12万1604棟で、このうち全壊は3175棟、大規模半壊は2167棟、半壊は1万1643棟だった。では阪神の教訓を発信しようと現地に入ったが、過疎高齢化が進む中山間地と、都市部の被災地とでは置かれた状況が違う。過疎の問題にも思いをはせ、復旧だけでなく、復興まで活動が広がった」
-この30年で、ボランティアは身近になったと言えるのでしょうか。
「中越地震以降、全国各地でボランティアに参加したり、活動を目の当たりにしたりする機会が増えた。かつての被災地が、現在苦しんでいる被災地を救援する『被災地のリレー』も生まれている。一方で、能登半島地震の被災地でボランティア不足が続いた場合、この流れが止まるのではないかと危惧している」
-能登半島地震以降も「被災地のリレー」をつなぐために、留意すべきことはありますか。...