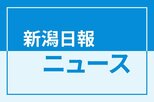死者・行方不明者6400人超、60万棟以上もの家屋が被害を受けた阪神大震災から1月17日で30年となる。2024年元日の能登半島地震で新潟市西区を中心に甚大な家屋被害をもたらした液状化現象水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。東日本大震災でも発生した。は、阪神の被災地でも起きていた。特に神戸市沿岸の埋め立て地で広域的に発生。地割れが起き、泥が噴き出した。今やその痕跡は見えないが、30年という時間の経過とともに、液状化に対する意識の風化が広がっている。地震研究の専門家とともに新潟日報社の記者が現地を歩き、あらためて震災被害を見つめ直した。

神戸市の玄関口、三宮(さんのみや)から南に約2キロの場所にある人工島「ポートアイランド」。集合住宅や学校、港を抱える4...
残り1538文字(全文:1838文字)