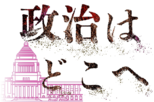県政界流動化 本腰入らず
上越新幹線の空港乗り入れ構想を練った国鉄OBの鬼頭誠と五十嵐豊(66)。田中角栄が倒れた後、2人が頼ったのは官民で「空港問題研究会」をつくっていた亀田郷土地改良区理事長の佐野藤三郎だった。
佐野は「すばらしい計画だ」と絶賛。旧大蔵省など各省庁幹部と気脈を通じていた佐野は霞が関に協力を仰ぎつつ、地元の機運醸成にも動き出した。
一方で県選出衆院議員で官房副長官などを務め、次代のエースと目された近藤元次も「大いに賛意を示してくれた」(五十嵐)。1989年に知事に就いた金子清(89)は91年に策定した「にいがた21戦略プロジェクト」に構想を加えた。
国鉄民営化に尽力した松田昌士(後のJR東日本会長)も「速度300キロの超特急で空港までつなげましょう」と乗り出した。
ところが、計画は急に失速する。
金子が佐川急便事件に巻き込まれ、92年に失脚。さらに近藤が94年2月、佐野が同年3月に相次いで死去した。田中の番頭格だった元厚相小沢辰男も、田中が政治の表舞台を去った後、急速に影響力を落とした。

政治構造の変化も一因になったとされる。
「96年に衆院選が中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に変更され、国政と県政界が流動化したことに尽きる」。県議会議長や栃尾市長を務めた馬場潤一郎(81)は断言する。
同じく県会議長や自民党県連幹事長などを歴任した元県議高橋正(86)は「空港乗り入れは県単独レベルではなく、国家レベルのプロジェクトにすべき案件。小選挙区制で国会議員が弱体化し、相対的に知事の政治力が高まり、県レベルで堂々巡りの議論をしてしまった」とみる。
金子の後、92年に日銀出身の平山征夫(77)が与野党相乗りの支援を得て知事に就く。「多方面からの支援を得たことで、八方美人的な行動をせざるを得なくなった。採算性などを巡って反対の声もあった空港乗り入れを『えいやっ』と進めるような政治判断はできなかった」と平山の元側近は証言する。
2004年、平山の後任となったのは泉田裕彦(59)。空港乗り入れに前向きな姿勢を見せることもあったが、3期12年で構想は前進しなかった。
北陸新幹線の建設負担金の支払いを一時拒否するなど「国に物申す」手法で物議を醸した泉田。「空港乗り入れを国家プロジェクトにするために国とのパイプを太くするどころか、細めてしまった」と自民県連幹部だった元県議は語る。
■ ■
衆院選が小選挙区制になって、本県では特に自民党の有力国会議員が減った。閣僚を輩出していない期間は本県が全国で最長だ。相対的に、後援会組織を持つ県議の力が強まった。
高橋は語る。「角栄先生は地元の旧新潟3区以外にも県全体、日本全体のビジョンを持っていた。だが次第に、県議が県予算を地元にどう持ってくるかのぶんどり合戦みたいになった」
2009年から自民党県連会長を過去最長の7年間務めた県議星野伊佐夫(82)は、力の源泉が知事泉田との「パイプ」だった。ただ、地盤が長岡市だったこともあり、空港乗り入れに強い関心を寄せることはなかったという。
「2000年代以降は星野氏に限らず県議会全体で空港乗り入れに本腰を入れていたかと問われれば、そうではなかったと言わざるを得ない」と高橋は述懐する。
16〜18年に知事となった野党系の米山隆一(54)は乗り入れ構想を「逆転本塁打」に例え、「それを狙って素振りだけしているのは非現実的」と否定的だった。新幹線延伸の機運はさらにしぼんでいく。(敬称略)