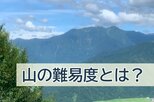海や川を見つめる長期企画「碧(あお)のシグナル」の5月シリーズは「魚尻(うおじり)」の視点を通し、流通や小売りの変化を追います。(6回続きの1)
魚が行き着く終点-。そんなイメージを連想させる言葉がある。「魚尻」。交通手段が限られた江戸時代や明治時代、生魚の鮮度を保ち、運べた範囲を指す。日本地理学会会長も務めた地理学者の田中啓爾(けいじ)(1885〜1975年)は著書「塩および魚の移入路」(57年)で各地の例を調べ、聞き取りも重ね、魚尻の姿を示した。
県内を起点とするのは柏崎から六日町(南魚沼市)、直江津(上越市)から長野、糸魚川から松本(長野県)といった経路があり、この魚の通るルートを魚尻...
残り2438文字(全文:2738文字)