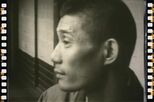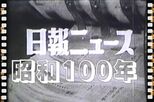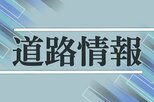1959年のニュース映画「新潟日報ニュース」
子供の代名詞にもなっている鼻たれ小僧を、最近はすっかり見かけなくなった。その理由は医学界でも長らくはっきりされないできたが、最近では「食生活の向上」が一番の原因といわれるようになった。裏付け調査した医師は「学校給食が減少に大きく貢献したことも見のがせない」といっている。【昭和48(1973)年12月7日「家庭」面】

学校での楽しみの一つ、給食は子どもの栄養改善に大きな影響を与えた。時代とともにメニューも変わり、内容も充実している。
日本の学校給食は1889(明治22)年、山形県の小学校で貧困児童を対象に無料で提供したのが始まりとされる。新潟県で給食が始まったのは1932(昭和7)年だが、戦争で一時中断した。
戦後、給食は再開されるが、当時は食糧難の時代で、汁物と脱脂粉乳だけといった献立だったという。県立大人間生活学部の太田優子准教授=栄養教育=は、「エネルギーやタンパク質などが足りず、バランスも悪かった。低栄養児をいかに減らすかが重要だった」と指摘する。
54年には「学校給食法」が成立し、実施体制が法的に整った。給食が普及していく中、「注目すべきは体のもとになる『タンパク質』の摂取量が増えたことだ」と話すのは、県立大人間生活学部の田邊直仁教授=公衆衛生学=だ。
田邊教授によると、昭和20年代は衛生環境や食糧事情が悪く、免疫力が低い低栄養児は...
残り647文字(全文:1227文字)