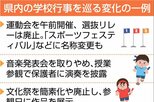早朝から鳴り響く音楽は必要なのか-。長岡市の山あいや農業が盛んな地域に整備されている防災無線について、越路地域の読者から新潟日報の「もっとあなたに特別報道班(もあ特)」にこんな意見が寄せられた。安眠妨害になっているという。市内では防災無線は合併旧町村の7地域にあり、うち越路など5地域では朝に音楽を流している。現状を調べ、考えてみた。(長岡支社・村山穂波)
防災無線は屋外スピーカーや各家庭に配った受信機を通し、行政の連絡や災害時の避難情報を放送する。
長年、越路地域に暮らす男性(63)の家の近くにはスピーカーがある。歳を重ねるにつれ、朝6時の「エーデルワイス」の調べで目が覚めるようになった。泊まりに来た1歳の孫も、音楽で目を覚ましてぐずった。「安眠の妨げではないか」。男性は首をかしげる。
越路では合併前の1989年、非常時の放送や行政、JAの情報を伝えるために防災無線を導入した。2004年に定期放送を終えたが、23カ所にあるスピーカーからは朝だけでなく、正午に「雪ぼたる」、午後6時に「夕焼け小焼け」がそれぞれ約1分間流れる。
和島、寺泊、与板、川口の各地域でも1日3回、三島地域では昼と夕方の2回、音楽やチャイムが鳴る。
■ ■
なぜ音楽を流すのか。05年から防災無線の設備を管理する市危機管理防災本部によると、「災害時に正確に機能するようにしておくため」だという。
直近では2019年10月13日に台風19号が上陸した際、越路、三島など7地域で避難情報が放送された。
住民に危険を知らせる手段が、知らない間に壊れていては確かに困る。
だが、早朝から音楽を流すのはなぜか。男性が疑問を寄せた越路地域の市支所地域振興課の小林哲課長は「雷の影響などで数年に1回程度だが不具合が起きるため、動作確認が必要」と説明。午前6時という時間帯については「以前から6時に放送していたので、続けている」と語る。
午前6時半と正午、午後6時に音楽を流す寺泊支所地域振興課は「帰宅が遅く、朝にしか家にいない人もいる。できるだけ多くの人に聞いてもらい、機器を点検する機会を確保しておくことが大事だ」と話す。実際それぞれの地域で音が聞こえないと連絡を受け、直したことが何度かあった。
住民の反応はさまざま。与板町与板の50代女性は「朝の農作業に区切りをつける時間が分かって助かる。昔から当たり前にあるのでなくなると困る」と語る。
■ ■
早朝にスピーカーから流れる音楽は、防災無線がきちんと機能しているかを毎日、大勢の耳で確認するために流されていた。
しかし、大音量に不快や疑問を感じる人もいる。これまで複数の支所に「チャイムがうるさい」という声が届いたこともあったが、危機管理防災本部が管理しており、個別対応は難しかったという。現時点でも防災本部は「全体での見直しは考えていない」とする。
疑問の声を受け、越路支所は意見の出た町内会の全世帯に対し、7月にアンケートを取った。約8割の223世帯が回答し、75%が「必要」としたため、当面は継続していく方針だ。ただ、もあ特に疑問を寄せた男性は納得いかない様子。「午前6時に流す根拠を示してほしい」と話す。
受け止め方がそれぞれ異なる朝の放送。みんなが納得できる丁寧な議論がこれからも必要そうだ。