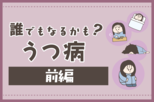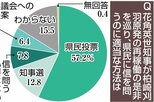被災者が早く自宅に戻れるようにしたい。仮設住宅の建設も早めたい。そのためには上下水道や道路などインフラの復旧を急がねばならない。
能登半島地震が発生してから1日で2カ月となった。石川県によると、亡くなった人は災害関連死の15人を含め241人、住宅被害は7万5421棟に上る。
県内の1万1449人が避難生活を余儀なくされている。体育館や集会所などの1次避難所に6587人、2次避難の前に一時的に受け入れる1・5次避難所に129人、ホテルなどの2次避難所に4733人が身を寄せている。
仮設住宅は県が2月末までに着工した3522戸のうち、302戸が完成したのにとどまる。
地震発生直後は最大で約11万戸が断水した。取水施設や浄水場のほか、配水管も各地で損傷したため、今なお約1万8880戸で断水が続いている。
水が使えなければ、被災者が避難所から自宅へ戻って生活をすることは困難だ。まとまった数のボランティアを受け入れることも容易ではない。
県はボランティアに関し、水道や道路の復旧遅れなどを理由に、個別の被災地入りを控えるよう呼びかけている。
しかし、被災者の生活再建にはボランティアの活動拡大が欠かせないはずだ。
行政には、宿泊拠点を設置するなどの工夫をして、被災地に滞在できるような受け入れ態勢を整えてもらいたい。
下水道被害も深刻だ。感染症など衛生環境の悪化が懸念される。能登半島の6市町は全体の3割の下水管が機能を回復していない。
最大震度7の強い揺れに地盤の液状化が重なり、下水管が寸断されたとみられる。
上水道と下水道の復旧をそろえないと、汚水があふれ出す恐れがある。上下水道の一体的な復旧を進めていく必要があるだろう。
被災者がトイレ利用を控え、体調を崩さないかも心配だ。
下水道を使えない地域では、仮設トイレや、水洗機能を備えたトイレトレーラーを置いている。
全域で量、質ともに足りているのかが気になる。行政にはきめ細かな対応を求めたい。
専門家は「三方を海に囲まれている能登半島の復興には道路復旧が不可欠だ」と指摘する。
北陸地方整備局によると、半島を縦断する能越自動車道で178カ所、海岸部を結ぶ国道249号で231カ所の崩落や亀裂などが生じている。
被災地支援で物資や資材を運ぶ幹線道路だ。緊急復旧は進んでいるが、輸送車や住民らが円滑に移動できるようさらに急ピッチで道路整備に努めてほしい。