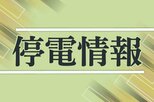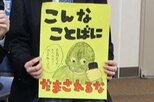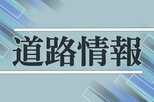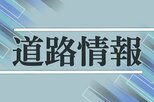政府は東京電力福島第1原発事故の発生以降に掲げていた「原発依存の低減」を改め、原発を最大限活用する方針に転換しました。12月からは新潟県の柏崎市と刈羽村に立地する東電柏崎刈羽原発の再稼働に向け、資源エネルギー庁が新潟県内28市町村を回って説明会を開く異例の対応を行っています。
こうした動きや再稼働問題を新潟県民はどう受け止めているのでしょうか。新潟日報社では、全会場の様子を取材し、質疑応答で語られた率直な声を順次紹介していきます。
【上越会場の主な質疑】
参加者 25人
回答者 資源エネルギー庁原子力立地政策室長

Q(男性) 原発は絶対安全とは言えないと思う。柏崎刈羽原発で事故が起きた時に、安全に住民の命を守るという保証を誰ができるのか、誰が責任を取るのか。
A 原子力規制委員会が科学的、技術的に厳正に審査し、基準に適合したものでなければ動かさない仕組みになっている。その上で、事故が起きれば事業者はもちろん、国も収束に当たる。国民の生命、身体財産を守るのが国としての責務。賠償についても事業者がその責任を果たせるような制度として整えている。
Q(女性) 北朝鮮から飛んでくるミサイルにはどう対応するのか。
A 原子力施設へのミサイルによる武力攻撃に対しては、PAC3(地対空誘導弾パトリオット)のような迎撃により対応する形がある。ほかに、事態対処法、国民保護法という法律があり、その中で原子力規制委員会が原子力施設の使用停止を命令する仕組みなどがある。
Q(男性) ドイツのように原子力発電を志向していない国もある。なぜその方向を追求しないのか。
A 資源が少ない中で、あらゆる電源を使っていくことが大事。国ごとに考え方が異なり、置かれている条件も違う。ドイツは(風車に適した)平地が多いが、日本はあまり多くない。そういった自然条件の違いがある。世界の動向も見ながら、現実に即したエネルギー政策としていきたい。
Q(男性) 避難計画は絵に描いた餅だ。上越市の一部にも避難準備区域(UPZ)があるが、風向きも変わるし、想定の通りにはならない。
A 避難については、風向きによって状況が異なる場合もある。実際のデータから判断を行っていく仕組みになっている。
Q(男性) 柏崎刈羽原発が再稼働しても、電気は東京の方に行く。新潟にメリットはあるのか。
A (柏崎刈羽が)動いたところで、例えば、料金などはあまり変わらないという指摘もある。どういったことで地域の振興あるいは貢献に役立つかは、原子力関係閣僚会議でも検討の指示が出ているので、しっかりと考えていきたい。
Q(男性) 今県民投票の動きが出ている。県民投票が行われて反対が多数になったら、国は再稼働を諦めるのか。
A、地方自治の中での議論で、国側として何か申し上げるのはおかしいと思う。私どもとしては、地域のご理解を得るように取り組んでいくということに尽きる。
Q(男性) 原発よりも、むしろ新しい自前のエネルギー開発に取り組んでほしい。
A 資源開発は非常に重要なこと。メタンハイドレートを商業ベースで取れるための、技術開発の支援を行っている。
Q(男性) 電力は現状不足していないという感覚なのだが。
A スイッチを押すと電気はくる。東京の方でも、持っている感覚じゃないかと思う。ただ、私どもから見ると、近年東日本の予備率が3%台ということも相次いだ。決して、余裕ある状況ではないと考えている。
Q(男性) 核燃料サイクルは破綻していると思うのだが、続けるのか。...