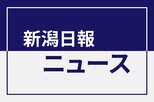政府は東京電力福島第1原発事故の発生以降に掲げていた「原発依存の低減」を改め、原発を最大限活用する方針に転換しました。12月からは新潟県の柏崎市と刈羽村に立地する東電柏崎刈羽原発の再稼働に向け、資源エネルギー庁が新潟県内28市町村を回って説明会を開く異例の対応を行っています。
こうした動きや再稼働問題を新潟県民はどう受け止めているのでしょうか。新潟日報社では、全会場の様子を取材し、質疑応答で語られた率直な声を順次紹介していきます。
【佐渡会場の主な質疑】
参加者 24人
回答者 資源エネルギー庁原子力立地政策室長

Q(男性) 佐渡島は東京電力柏崎刈羽原発(から半径)30キロ圏外だが、東電福島第1原発の事故では、風向きによって放射性物質が30キロ以上飛んだと思う。島外へは自力で移動できない。(事故があった場合)どのように避難すればいいのか。
A 風向きによっては30キロを超えてしまうこともある。放射線量を測定することで避難の在り方を判断することになる。屋内退避を指示する可能性はある。
万が一だが、全員避難のケースを想定すると、1週間程度以内に一時移転することになる。離島なので限界はあるが、海路と空路で実働部隊が救出に向かう。
Q(同) 避難する場合、誰が具体的にルートを決めるのか。
A 政府の原子力災害対策本部が、県、市と連絡を取りながら避難ルートを指示する。放射線被害の状況によってルートは変わる。
Q(男性) 海洋が汚染された場合、漁業関係者は大変だ。
A 福島の事故でも以前のように、漁ができなくなった。この場合の補償、賠償は電気事業者が責任を負う。事業者が支払えない場合に備え、国が事業者にいったんお金を渡して賠償する制度もある。
Q(男性) 福島の原発事故の被害を丁寧に説明してほしい。柏崎刈羽原発で同じ事故が起きた場合、新潟県や佐渡でどの程度の被害になるのか図で示してほしい。(国は)再稼働する前提で考えているようだが、納得できない。
A 福島の事故(への対応)は道半ばで、避難を余儀なくされている方、自主避難の方も含めて約2万5千人いる。事故の教訓を踏まえて、新しい規制基準が作られており、安全性の基準は当時とは異なる。ただ、想定外のケースを踏まえて不断の安全性向上に取り組むこととしている。
事故が起きた場合は、まず30キロ以内で想定している。佐渡には(放射線量を測定する)モニタリングポストが2カ所あり(羽茂本郷の南佐渡消防署と関岬)、状況によって避難の考えを切り替えていく。
Q(男性) 福島原発事故では、情報提供が遅かった。自主的に屋内退避をするためにも迅速な対応を求めたい。
A 福島事故では情報発信に混乱があり、...