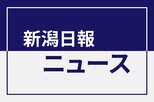政府は東京電力福島第1原発事故の発生以降に掲げていた「原発依存の低減」を改め、原発を最大限活用する方針に転換しました。12月からは新潟県の柏崎市と刈羽村に立地する東電柏崎刈羽原発の再稼働に向け、資源エネルギー庁が新潟県内28市町村を回って説明会を開く異例の対応を行っています。
こうした動きや再稼働問題を新潟県民はどう受け止めているのでしょうか。新潟日報社では、全会場の様子を取材し、質疑応答で語られた率直な声を順次紹介していきます。
【新潟会場の主な質疑】
参加者 53人
回答者 資源エネルギー庁原子力立地政策室長
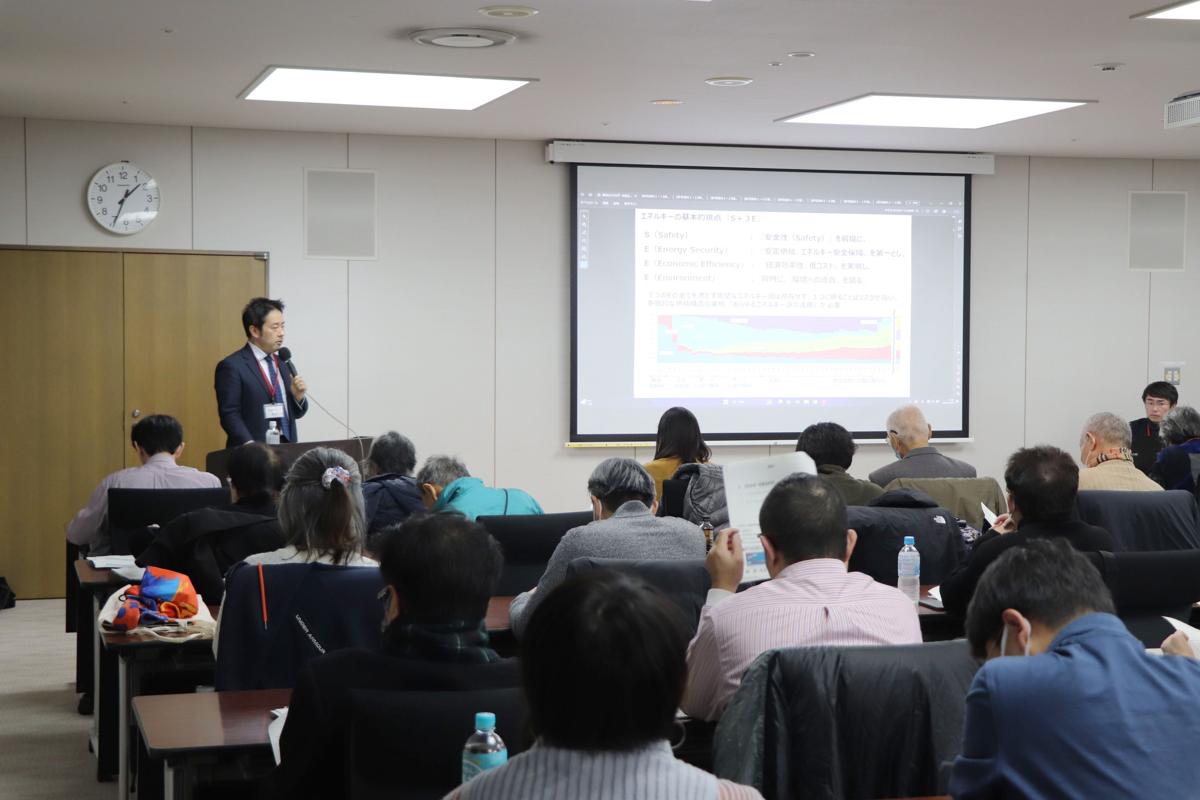
Q(女性) 国や自治体も、原発で事故が起きれば的確な行動ができないのではないか。
A 事故が起きれば対策本部がつくられる。しっかり機能するよう訓練を重ねて、対応の実効性を上げていく。
Q(女性) 放射性廃棄物の処分は将来につけを残す。次世代型の太陽光電池があれば、原発の新増設は必要ないのではないか。
A 日本では(最終処分の)場所が決まっていない。社会全体で解決するべき問題で、できるだけ多くの地域に関心を持ってもらえるよう活動している。全国の原発は、営業運転から40年が経過するものが多くなっていく。脱炭素と安定供給を考えれば、新しく建て替えていくことも大事だ。再エネも活用を進める。例えば、ペロブスカイト太陽電池は、曲げることができるので、敷き詰める余地が広がる。
Q(女性) 他のエネルギーと比べて、原発はコストが安価だというのは疑問。
A (試算では)核燃料サイクルや事故リスク対応などを盛り込んだ費用を示した。必ずしも全ての電源で同様の比較をしているわけではないが、コストは他のエネルギーと遜色ない水準とみている。
Q(女性) 今回の説明会、なぜ(経済産業省)資源エネルギー庁が原子力規制委員会の資料を説明するのか。
A 今回は...