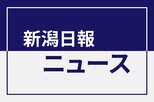国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者になろうとしている2025年、高齢者に多い疾患を巡り、県内の医療機関がある事態に危機感を募らせている。心臓の機能が低下し、さまざまな症状を引き起こす心不全何らかの原因で心臓のポンプ機能が低下し、臓器をはじめ全身に必要な血液を十分に送り出せなくなる状態のこと。病名ではなく、心筋梗塞など心臓のさまざまな病気や高血圧などにより、負担がかかった状態が最終的に至る「症候群」と捉えられている。息切れやむくみ、疲労感など、さまざまな症状が引き起こされる。患者の急増だ。病床数には制約があり、治療する循環器医は医師少数県の新潟県でも特に少ない。「心不全パンデミック(大流行)」に直面する循環器医療の現状と課題を追った。
3月上旬。新潟市西区の「青山内科・眼科クリニック」の一室で、心不全の患者が自転車型の運動機器のペダルを回す。医師らが心拍数や息切れの様子などを見守る中、約30分間、一定のペースで負荷をかけていく。運動療法と生活指導などを組み合わせる「心臓リハビリテーション心不全など心臓病の患者が、快適な生活や社会復帰、再発防止を目的として行う医療プログラム。患者の状況に応じて運動療法と学習活動、生活指導などを組み合わせる。(※ページ下部に詳細)」だ。
心不全で手術、退院後、昨年12月から心臓リハビリに通う会社員の男性(43)は「血圧や体重は自分で測れるが運動の程度は自分で分からない。ここに来て、これくらい動いていいんだと分かる」と笑顔を見せる。
心不全患者の入院増加による医療逼迫(ひっぱく)を防ごうと、症状を安定させ再入院を減らす取り組みが進んでいる。適切な運動を続けることで体力を向上させ、心臓の負担を減らし病気の再発を防ぐ。
新潟県で心臓リハビリができる施設は15ほどある。同クリニックは、...