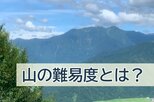新潟日報に掲載された記事の中から、ウェブサイトユーザーにもぜひ読んでほしい紙面(記事)をピックアップします。
× ×
新潟県警など全国の多くの警察が犯罪捜査の写真記録用に、改ざんの余地がある東芝メモリ社製のSDカード「ライトワンスメモリカード東芝が2011年に発売した改ざん防止機能付きのSDカード。現在は東芝メモリ社が製造している。同社ホームページでは「動作確認済みのデジタルカメラで撮影した原画像ファイルに対して編集・加工または消去ができない記録媒体」と説明し、改ざんはできないとしている。同じカードを複数のカメラで使用することを禁じるなど、いくつかの注意事項が設定されている。」を使用していることが判明した。新潟日報社は、パソコンなどを使って画像を加工し、その画像を別のライトワンスカードにコピーして原本を装えることを確認した。デジタルカメラの内蔵メモリーでも同じようなことができた。業界関係者の話も交えて検証した。
【2018/10/04】
カード内の画像を編集したり加工したりする場合、パソコンを使う方法と、専用カメラの内蔵メモリーを使う方法がある。
パソコンを使った検証は、(1)専用カメラで車の写真を撮影(2)画像をパソコンにコピー(3)画像加工ソフトで別の車のナンバープレートと置き換え(4)画像を別のカードにコピー-の手順で行った。比較的簡単に加工し、画像を保存することができた。原本とは別の“新たな原本のカード”が作成できることになる。
業界関係者によると、パソコンを使った場合、写真に写っている建物や人物などを消すこともできる。本来は写っていないものを加えることもできる。撮影日時を書き換えることも可能という。
デジタルカメラの内蔵メモリーを使った場合でも、カメラ上でトリミングや色調整などを行うことが可能だった。この場合も、別のライトワンスカードにコピーすることができ、“新たな原本”を作成できた。警察庁の担当者は「パソコンを使うことはそもそも想定していないが、仮に加工などをすれば痕跡が残る。ばれるようであれば、改ざんなどはしないだろう」と話す。

改ざん防止機能があるSDカードは他社製もある。しかし、ライトワンスカードの方が価格が安いとされ、一般競争入札で落札されやすい面もあるため、普及が進んでいないとみられる。
大阪地検特捜部の主任検事がフロッピーディスクの内容を改ざんした事件の発覚につながった厚生労働省文書偽造事件の弁護団の一人は「自分たちは改ざんしないから改ざんは防げると言っているだけ。問題が生じないようにするには改ざんの可能性が全くないカードを使用するのが当然だ」と指摘した。
◆検事が、警察官が…証拠品や調書のねつ造・改ざん、過去に何度も
警察や検察などの捜査機関による証拠品や調書のねつ造と改ざんは、これまで何度も行われてきた。弁護士らの中には、冤罪(えんざい)を防ぐために、全面的な証拠開示や取り調べの可視化が欠かせないとする声があるが、実現していない。
捜査機関による証拠品の改ざんが行われた事件としては、元厚生労働省の女性職員(後に事務次官)が逮捕、起訴された文書偽造事件がある。この事件を巡っては、2010年に大阪地検特捜部の主任検事が、押収したフロッピーディスクの内容を書き換えていたことが発覚した。
2002年に富山県氷見市で発生した女性暴行事件では、男性が逮捕、起訴され、服役中に真犯人が見つかる事案が起きた。捜査に当たった富山県警は、誘導的な取り調べを行い、虚偽の調書をつくり出すなどしていた。
弁護士が捜査機関による証拠のねつ造などを指摘し、再審を求めている裁判もある。
冤罪とは別に、警察官が自らの都合によって証拠品のねつ造や改ざんを行っていた例もある。10年には大阪府警堺署の刑事が、覚せい剤取締法違反事件の証拠品だった注射器が無くなっていると思い込み、無関係の注射器を準備して証拠品としてねつ造した。
このほかにも警察官が交通事故の捜査で、実際には取り調べをしていないにも関わらず参考人調書をねつ造する事件などが、全国で起きている。