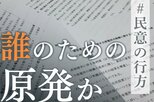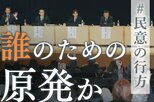東京電力柏崎刈羽原発1985年に1号機が営業運転を開始した。全7基の出力合計は821・2万キロワットで世界最大級だが、2023年10月現在は全基停止中。東京電力は2013年に原子力規制委員会に6、7号機の審査を申請し、17年に合格した。その後、テロ対策上の重大な不備が相次いで発覚した。終了したはずだった安全対策工事が未完了だった問題も分かった。の周辺住民の安全確保を目指し、新潟県と柏崎市、刈羽村は東電と「安全確保に関する協定書(安全協定)1983年10月に県、柏崎市、刈羽村が東京電力柏崎刈羽原発周辺住民の安全確保のため東電と締結。原発の安全規制を行う国だけでなく、地元も原発が安全に管理されているかを常に確認できるようにした。法律ではなく、協定の内容を破っても罰則はない。全19条からなり、施設の新増設、変更時は東電が自治体の事前了解を得ることを定める。原発への立ち入り調査、技術委員会の設置のほか、自治体が必要と認めた場合、国を通じて原子炉の運転停止を含む適切な措置を要求することができる。」を結んでいる。協定は、自治体が東電に対し、原子炉の運転停止を含むさまざまな要求をするための根拠となっている。その性質や原発の安全に対する自治体や住民の関わり方を、安全協定に詳しい関西大准教授(リスク・ガバナンス)の菅原慎悦氏(40)に聞いた。(論説編集委員・仲屋淳)
-安全協定の意義をどう考えますか。
「2011年の東電福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東電福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。を教訓に安全性向上の対策がどう作られてきたかを見て、原子力を巡る安全は電力会社の取り組みだけでは完結しないと思った。福島事故では病院から避難する過程で患者が亡くなる事態もあった。安全は、自治体など関係機関が有機的につながってこそ総合的に成り立つ」

「安全協定は本来、電力会社が勝手に物事を進めることを抑制する面がある。一方で、地元と...