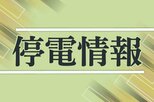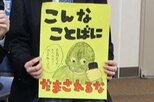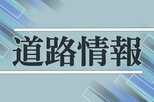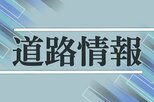政府は東京電力福島第1原発事故の発生以降に掲げていた「原発依存の低減」を改め、原発を最大限活用する方針に転換しました。12月からは新潟県の柏崎市と刈羽村に立地する東電柏崎刈羽原発の再稼働に向け、資源エネルギー庁が新潟県内28市町村を回って説明会を開く異例の対応を行っています。
こうした動きや再稼働問題を新潟県民はどう受け止めているのでしょうか。新潟日報社では、全会場の様子を取材し、質疑応答で語られた率直な声を順次紹介していきます。
【阿賀野会場の主な質疑】
参加者 20人
回答者 資源エネルギー庁原子力立地政策室長
Q(男性) 新潟は農業県であり、広い農地でコメを生産している。漁業や観光面でも柏崎刈羽原発の存在はデメリットだと思う。廃止してほしい。
A 新潟でコメが生産され、首都圏も恩恵を受けていることに思いをいたさなければならない。原発に対してはすぐに廃止するべきだという声も、使うべきだという声も日々受けている。それぞれを受け止めながら、今のエネルギー政策では電力の安定供給を果たし、環境適合を図り、コストもなるべく上げないために、原発についても最大限活用する方向を示している。
Q(男性) ウクライナがロシアに侵攻され、原発が攻撃された。日本でも原発が狙われたら怖い。テロも心配だ。
A イージス艦や迎撃ミサイルなど防衛システムが多重にある。外交も含め、国防上の問題として対応していく。テロ対策も非常に大事だ。原発への侵入者を防ぐさまざまな対策が施されており、原子力規制委員会が確認している。
Q(男性) 次世代の「ペロブスカイト太陽電池」は有望ではないか。
A ペロブスカイトはとても重要で、従来の太陽電池よりも非常にいい技術。予算を振り向け、技術開発や実用化を推進している。
Q(男性) 住民として最も知りたいのは、原発事故時にどう避難すればいいのかの具体的な説明だ。
A 万が一、原発から放射性物質が放出された場合、まずは原発から半径5キロ圏と5〜30キロ圏の住民に対応してもらう必要がある。阿賀野市など30キロ圏外については、原発の状況や放射性物質がどう拡散しているかをモニタリングし、情報提供していく。東京電力福島第1原発事故の反省を踏まえ、どこからどこへどう逃げるかなどはあらかじめ避難計画に書かれている。政府としても周知、広報に努めていく。
Q(男性) 福島第1原発の廃炉には何十年もかかる。事故の影響はまだ続いている。それなのに、原発の可能な限りの低減から最大限活用に方針転換するのはなぜか。...