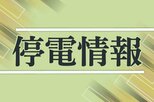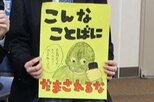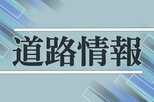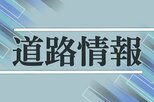政府は東京電力福島第1原発事故の発生以降に掲げていた「原発依存の低減」を改め、原発を最大限活用する方針に転換しました。12月からは新潟県の柏崎市と刈羽村に立地する東電柏崎刈羽原発の再稼働に向け、資源エネルギー庁が新潟県内28市町村を回って説明会を開く異例の対応を行っています。
こうした動きや再稼働問題を新潟県民はどう受け止めているのでしょうか。新潟日報社では、全会場の様子を取材し、質疑応答で語られた率直な声を順次紹介していきます。
【聖籠会場の主な質疑】
参加者 5人
回答者 資源エネルギー庁原子力立地政策室長

Q(男性) (放射性廃棄物の)最終処分場がまだ決まっていない。原発が稼働すれば、廃棄物が一杯になるのではないか。
A 日本においては放射性廃棄物を再処理していく方針。その施設が稼働していないので、高レベル放射性廃棄物が大量に出てくる状況ではない。再処理施設の竣工と、最終処分地の選定にしっかりと対応していきたい。
Q(女性) こうした説明会は(原発)立地地域以外でも行っているのか。そこではどのような意見が出ているか。
A 全国で説明の機会を設けている。年間で100回ほどになるかと思う。エネルギーの見通しに関する意見もあれば、原子力に関心を持っている方も多くいる。(放射性廃棄物の)最終処分の場所が決まっていないのは大丈夫なのかとか、再エネでまかなえるのではないかとか、さまざまな意見をいただいている。
Q(同) 新潟県では東京電力(柏崎刈羽原発)の電気を使っていない。リスクだけだ。新潟県民にとって、原発が立地していいことは何なのか。
A 柏崎刈羽原発が稼働することによって、東北電力管内で電力に余裕がない場合に融通することができる。東日本エリア全体の需給ひっ迫に対する懸念の解消につながる。その上で、電気を使っている側としてのありがたみを新潟県内に還元することも大事。その制度の一つとして、電源立地地域への交付金を国から県に渡している。
Q(男性) 原発のテロ対策について、いざというときに機能するか不安。アメリカの同時多発テロのような事案とか、弾道ミサイル(の着弾)も想定して、対策や避難計画に生かされているのか。...