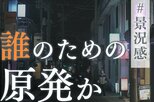東京電力柏崎刈羽原発が立地する新潟県内の地元地域では、地域活性化のためにと原発の運転再開を望む声が聞かれる。再稼働は地域の光となるのか。新潟日報社は長期企画で、新潟から原発を巡る疑問を考えていく。今シリーズでは地域経済に貢献しているのかを検証する。=敬称略=(12回続きの3、地域経済編「企業収益」の上)
トラックから下ろされた鉄骨が、バーナーで細かく分解されていく。2023年12月中旬、新潟県柏崎市の資源リサイクル業「宮田才吉商店」の工場では、従業員がビルの廃材を再利用するための作業に励んでいた。
2023年春に創業100年を迎えた老舗は、紙類の収集から事業を始め、工事現場や工場から出る金属くずなどの処理に手を広げた。

資源リサイクル業「宮田才吉商店」=柏崎市藤井
1978年に始まった東京電力柏崎刈羽原発の建設工事も商機だった。「原発は鉄とコンクリートの塊なので、スクラップが大量に出た」と3代目社長の宮田康雄(79)。当時は売上高の3割ほどを原発関連の仕事が占める年もあったという。
半世紀以上前、20代の時から原発の誘致、推進活動に取り組んできた宮田は「地元としてできる仕事には関わっていきたい」と力を込める。
東電福島第1原発事故を受けて2012年に柏崎刈羽原発の全号機が停止柏崎刈羽原発には1~7号機まである。このうち2・3・4号機は2007年の中越沖地震で被災して以降は動いていない。1・5・6・7号機は中越沖地震の後に順次運転を再開した。福島第1原発の発生時は4基が稼働していた。事故後に1、7、5、6号機の順に定期検査に入った。2012年3月に6号機が定期検査入りしたことで、全号機が停止する状態となった。した後も、安全対策工事などで出る廃棄物の処理を請け負ってきた。将来の廃炉に向けて柏崎市などが主催する勉強会にも参加し続ける。

資源リサイクル業「宮田才吉商店」で作業する従業員=柏崎市藤井
「脱炭素気候変動による被害を抑えるため、二酸化炭素やメタン、フロンなど地球温暖化の原因とされる物質について、大気への排出量を実質ゼロとすること。石油や石炭、ガスなどを燃やして排出される二酸化炭素などは温室効果ガスと呼ばれる。温室効果ガスが地球を覆うことで太陽の熱を閉じ込め、気温が上昇するといわれている。の観点からも、大量の電気を安定供給する原発は必要だ。再稼働すれば、地域の消費の活性化にもつながるはずだ」。宮田はそう強調する。
ただ現在、収益に占める原発関連業務の比率は高くない。堅調な業績を支えているのは、国内外のスクラップ需要の高まりだ。銅や鉄など各種金属の価格が高止まりしているという。SDGs2015年9月に国連サミットで採択された2030年までの国際的な目標。読み方はエスディージーズ。17のゴールと169のターゲットから構成される。貧困や不平等の撲滅、質の高い教育の確保、持続可能な生産と消費の在り方など幅広い分野に及ぶ。英語ではSustainable Development Goalsと表記される。(持続可能な開発目標)の浸透に伴い、資源の有効活用が進められていることが背景にある。
柏崎市には原発と歩んできた企業がある一方、基幹産業の製造業などからは「原発との関係は薄い」との声が聞かれる。原発の運転と停止は、地元企業の「稼ぐ力」に影響してきたのだろうか。
× ×