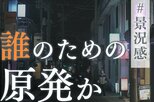東京電力柏崎刈羽原発が立地する新潟県内の地元地域では、地域活性化のためにと原発の運転再開を望む声が聞かれる。再稼働は地域の光となるのか。新潟日報社は長期企画で、新潟から原発を巡る疑問を考えていく。今シリーズでは地域経済に貢献しているのかを検証する。=敬称略=(12回続きの5、地域経済編「個人所得」の上)
日本海に面し、近隣の長岡市や上越市とは山で隔てられる新潟県柏崎市。かつては冬場、周辺地域とつながる道路が雪で通れなくなることもあり、自らの暮らすまちを「陸の孤島」と自嘲気味に呼ぶ住民もいた。
「そんな状況を打開し、市民が豊かになるには、大きなきっかけが必要だった」。柏崎商工会議所の元専務理事、内藤信寛(83)は、地元経済界が東京電力柏崎刈羽原発を誘致した当時を振り返る。

青色や赤色の屋根の工場群が並ぶ柏崎機械金属団地協同組合=2023年12月、柏崎市田塚(小型無人機から撮影)
柏崎商議所が原発誘致を決議したのは1969年3月。当時29歳だった内藤は商議所幹部らと全国各地の立地自治体を視察し、原発の有用性についての講演会を企画するなど、推進の旗振り役を務めた。
誘致活動は実り、柏崎市には立地に伴う交付金や固定資産税などが舞い込んだ。それらを財源に総合体育館や野球場など公共施設が整備され、道路をはじめインフラも充実。産業が活性化して家計を潤わせ、人々の暮らし向きが良くなっていくとの期待感が高まった。
「地理的に恵まれない条件の中で長年、街の規模を維持できた。原発が立地した効果はあった」。内藤は力を込める。

JR柏崎駅から近い商店街にある複合商業施設「フォンジェ」=2023年11月、新潟県柏崎市東本町
一方で、心残りも口にする。製造業など地元企業に原発関連の仕事への参入を呼びかけた。しかし、原発は機器一つにも専門性や高い技術が求められるといった事情もあり「笛吹けど踊らずだった」。エネルギーの街を標榜する柏崎市の将来を見据え、さらなる原子力関連の研究機関や施設の誘致も構想したが、実現することはなかった。
地元企業が携わる原発の仕事は、建設が終われば定期検査法律に基づき約1年(13カ月以内)に1回、運転を止めて必要に応じて行う原発の検査。点検の頻度などは機器ごとに異なり、一度の検査ですべての機器を点検するわけではない。検査の期間に基準はなく、通常は3カ月程度かけて行われる。検査は基本的に事業者が行う。定期事業者検査ともいう。が主になる。だから関連産業を育て、市民の雇用や所得を増やしたい-。そう思い描いていた内藤だが、現状を「昔に戻ったみたいだ」と感じている。

東京電力柏崎刈羽原発
「再稼働すれば街が良くなる。そんな精神面の期待ばかりが大きくなっている気がする」
× ×