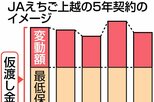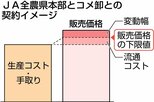新潟県は11月26日、2025年の県産主食用米の目標生産量を56万2400トンにすると公表した。米の品薄を受け、24年産の目標生産量54万6千トンを1万6400トン上回った。国による生産調整(減反)廃止後、県が生産目標の目安を提示するようになった18年産以降で最大となった。近年の作況や需要を踏まえた県の目標引き上げは、生産抑制基調の転換点となる可能性がある。
同日、新潟市中央区で開かれた県農業再生協議会で示され、了承された。
2024年産の実績は54万3500トンだった。目標生産量は18年産以降、51万〜54万トン台で推移していた。25年産の目標作付面積も10万3800ヘクタールで、県が同面積を提示するようになった21年産以降では最大だ。
目標生産量の設定に当たり県は、新米が出る前の6月末時点の民間在庫量を指標の一つにしている。これまで6月末の適正在庫量を年間需要量の2・5カ月分としていた。24年6月末も2・74カ月分在庫があったものの、品薄となった。
年間を通じた安定供給に向け、25年産は6月末時点の在庫目標を3カ月分に引き上げた。また23、24年産と2年連続で作況が「やや不良」となり、25年産は全国の需要に応える必要があるとして、生産目標を引き上げた。中食・外食需要が伸びているとし、コシヒカリ以外の中価格帯米の生産拡大を呼びかける。
県は非主食用米の作付けを促すための「産地交付金」を、25年度から変更する方針も示した。ことしの米価の大幅上昇を受け、主食用米への作付けが過剰になるのを防ぐため、非主食用米への支援を拡充する。

加工用米や、輸出用など「新市場開拓米」の支援額を10アール当たり6千円から同1万円に引き上げるほか、米粉用米への支援(同1万円)を新設。野菜や果樹など「高収益作物への転換拡大支援」(同2万5千円)は終了する。
◆過剰生産警戒も 非主食用米へどう誘導?
2024年産米の品薄を受け、県が26日に示した2025年県産主食用米の目標生産量は...