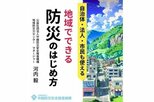能登半島地震への対応について議論した県議会の防災・脱炭素社会づくり特別委員会=2月5日、県議会
新潟県議会は2月5日、防災・脱炭素社会づくり特別委員会を開き、能登半島地震を受けた東京電力柏崎刈羽原発を巡る問題などを議論した。県議会議員は避難道路を国が整備することや、原発周辺の断層地面の下にある岩の層や地層に力が加わり、元々つながっていた面と面がずれた状態。面の食い違いそのものを指す場合もある。面のずれた割れ目(破壊面)に力が加わり、動くことを「断層運動」などといい、ずれ動いた時の衝撃が地面に伝わったものが「地震」となる。断層は陸地側(陸域)と海側(海域)それぞれにある。の再評価を求めた。
自民党の斎京四郎氏(上越市)は地震発生時に自宅の直江津地区から避難しようとしたが、渋滞が相次いだ経験を踏まえ「道路状況を改善してほしいと国に要望しているが、現実は非常に厳しいと実感した。避難計画都道府県と市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが求められる。また、原子力災害対策指針に基づき、原子力災害対策重点区域を設定する都道府県と市町村は、地域防災計画の中で対象となる原発などの施設を明確にした原子力災害対策編を定めることになっている。新潟県の広域避難計画は、地域防災計画に基づき策定されている。通りに逃げ切れるのか」と...
残り417文字(全文:629文字)